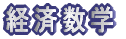決算書は、取引を集計した集計表であり、複式簿記は、取引を集計し、決算書を作成するための手続、操作である。会計は、手続、操作の基準、及び、規則である。:決算書の目的は、期間の経営業績を期間損益の規則に従って算出することである。
即ち、複式簿記は、取引の集合であり、取引を構成する要素は勘定である。故に、複式簿記は、取引の集合であり、元は、勘定である。会計、及び、複式簿記は群である。
勘定は、借方、貸方に類別(classify)される。故に、借方、貸方は、複式簿記における類(class)であり、会計の部分集合である。
又、借方は、総資産と費用によって構成される。総資産は勘定の集合であり、総資産の元は、資産に類別された勘定であり、費用の元は費用に類別された勘定である。借方は、資産と費用に類別される。故に、資産と費用は、借方の類である。
貸方は、総資本と収益によって構成される。総資産は、負債と資本(純資産)によって構成される。収益は、収益によって成り立つ。故に、総資本の元は、負債と資本(純資産)に類別された勘定であり、収益の元は、収益に類別される勘定である。
借方、貸方は、複式簿記の部分集合である。資産と費用は、借方の部分集合であり、負債と資本(純資産)、収益は、貸方の部分集合である。
故に、資産と費用と負債と資本(純資産)、収益は、複式簿記の部分集合である。
借方は、実質的勘定であり、貸方は名目的勘定である。
実質的な勘定は、人と物に関連し、名目的勘定は、金に関連している。
実質的勘定は、実物市場に結びつき、名目的勘定は、金融市場に結びついている。
実質的勘定は、財としての性格を持ち、名目的勘定は、形式的性格を持つ。
実質的価値と名目的価値の差は、主権の有無である。勘定に機能を発揮させる原動力は主体性にある。実質的勘定は、会計主体が能動的に関われる勘定であるのに対し、名目的勘定は受動的な勘定といえる。
例えば、売掛金や受取手形は資産勘定に属し、実質的勘定と見なせる。それに対し買掛金と支払手形は、負債勘定に属し、名目的勘定といえる。
売掛金、受取手形と買掛金、支払手形との違いは、買掛金や支払手形は約定に拘束されるが、売掛金や受取手形は、必ずしも、約定に制約されずに、財として固有の働きを持つことが可能である点にある。
約定に基づく勘定は、予め方程式が設定されているのに対し、相場による物は、不確実な要素である。
約定に基づく勘定は、原則的に名目的勘定と見なせる。ただし、減価償却費のような例外的な勘定もある。約定に基づくのは、金利、借入金、減価償却費、リース代、人件費などがある。
勘定は、貸借と損益に類別される。貸借は、資産、負債、資本(純資産)によって構成される。損益は、収益と費用によって構成される。貸借と損益は、勘定の集合であり、資産、負債、資本(純資産)は、貸借の類であり、収益と費用は、損益の類(class)である。
故に、損益は、複式簿記の部分集合であり、貸借も複式簿記の部分集合である。収益と費用は損益の部分集合であり、資産、負債、資本(純資本)は貸借の部分集合である。
同じ類の元になる勘定は、同値関係にある。
勘定は、類別された領域内では正の値を取り、領域の外では負の値をとる。
複式簿記は、取引の集合である。故に、複式簿記は、取引の認識に始まる。会計の始まりは、取引の認識と範囲を特定し、定義することである。
取引は、帳簿、或いは、伝票に記録することによって確定する。
取引は、取引が成立した時点において貸方、借方、二方向の勘定が同時に発生する。取引を構成する借方、貸方の値は、取引が成立した時点において均衡している。即ち、等しい。故に、借方と貸方を集計した値は、常に等しい。
複式簿記は、手続によって成立している。手続とは、複式簿記における演算、操作を順序づけした体系である。
複式簿記は、認識、仕訳、記録(記帳)、転記、締め、集計、決算仕訳の順に行われる。
そして、演算は、仕訳帳、総勘定元帳、試算表、精算表を経て、損益計算書と貸借対照表に集計される手順で帳簿上において演算、操作が行われる。
先ず、数量、或いは、単位時間の量を単価に掛け合わせ、経済的価値を貨幣価値に還元、統一する。その後、勘定(類、class)に仕訳し、同じ類の勘定を加算、合計する。その後、期間配分が必要な勘定を単位期間に配分し、借方、貸方の差によって損益、貸借の残高を計算する。
単価とは、一定の通貨単位による財の単位価格である。変動為替制度下では、通貨単位と他の通貨単位との交換レートは、為替の相場によって変化する。そして、変動為替制度下では、為替の変動に伴い各々の通貨圏毎に単価は変動する事になる。
日常取引においては、借方、貸方、同一領域内の同一勘定の値のみを合計する可算処理のみを行い。
即ち、現金は現金、備品は備品、消耗品は消耗品、商品は商品、売掛金は売掛金、売上は売上と同一の勘定間だけ、借方、貸方各々の側で加算処理される。
締め処理後に減産処理をして残高を計算する。
会計は、代数和の世界である。そして、同類項を集計する事によって成り立っている。会計は、原則的に加算主義である。
利益に対して、資産と収益は、正に作用し、負債と費用は負の働きをする。
利益とは、会計主体の期間損益を計るための指標、手段である。利益は、経営目的ではない。利益は、目的ではなく、一種の信号のような情報である。
いわば設定された目標のようなもので、前提条件と方程式によって定まる値である。故に、前提条件や方程式を変えれば、結果にも差が生じる。しかも、前提条件や方程式は、一定の制約上の下に任意に選択できる。つまり、自然現象のように客観的基準によって定められた方程式によって決まる絶対値ではない。
故に、利益を経営目的とするのは誤りである。利益の意味は、利益の働きから求められるべき概念である。
利益は、設定された前提条件と会計規則によって算出される値である。問題は、利益をどの様に設定するかである。それが会計上の規則(ルール)を構成する。利益は、経営目的と言うよりも会計上の目的であり、会計所の目的は、社会的目的に準ずるのである。
社会的目的は、会計主体の社会的機能から導き出されるものである。社会的機能とは、社会的分配機能にある。即ち、労働者、経営者、投資家、国家、社会、取引先に対し、適正な所得を分配することである。その為に、利益は会計的に設定されている。
会計運動は、収益を軸として収益、資産、費用、負債の相互作用によって起こされる。資本(純資産)は、収益、資産、費用、負債の働きに準じて決まる従属的変数である。
会計運動の原動力は資金であり、資金の調達力は、負債、資本(純資産)、収益に現れる。故に、勘定の性格は、利益と現金の動きに対して、どの様な働きをするかによって決まる。
収益が悪化すると、先ず、資金調達が圧迫される。その結果、資産の費用化の速度が鈍り、また、資産の流動化が始まる。また、資金不足から短期借入金が増大し、資産が圧縮されることによって長期借入金に対する返済圧力が強まる。資産の流動化と負債の増加によって資本が圧迫される。
長期借入金の返済原資は、利益処分に求められるが、利益処分の項目には、長借入金の返済項目がないために、長期借入金は、借り換えを前提とし、負債の項目に滞留することとなり、資本と同じ様な働きをするようになる。この長期借入金が収益が悪化するたびに蓄積される。
資金の調達は、収益による事を原則とする。収益は、利益に反映される。利益は、企業の収益力の指標、バロメーターである。つまり、利益の中から、配当と税と、経営報酬が支払われることによって収益状態を資金調達力に反映するのである。また、赤字の場合、収益と費用の均衡が悪い事を意味する。
赤字の要因には、収益の低下、費用の増大の二点がある。収益の低下は、市場の縮小、市場の過飽和、過当競争、購買力の低下、景気の周期、商品の周期、為替変動等がある。又、費用の増大には、原材料の高騰、市場独占、人件費の増大、政策的要因、金利負担の増加、償却費の増加、為替の変動、事故、災害の発生、物流費用の増加などがある。
収益力が低下すれば、長期借入金や資本(純資本)の回収圧力が強まり、投資資金が不足することによって企業の成長は止まる。
又、資金収支と期間損益には、ズレがある為に、期間損益の原則に従って利益処分を行うと、利益が上がってきた当初、長期借入金の返済が終わっていないのに、或いは、償却が終わっていないのに、利益処分によって新たな資金を調達せざるを得なくなることがある。又、一定の利益が確保されるようになっても市場の環境によって低収益率に甘んじなければならない状態に陥ることがある。
その為に、会計主体は、常に、慢性的な資金不足の状態に置かれている場合が多いのである。為政者は、この点を充分留意する必要がある。
勘定の性格は、会計の指標が利益であり、会計主体の原動力が資金であることから、利益と資金対する作用によって規定される。
勘定の性質は、現金勘定に対する勘定の位置と働きによって定まる。即ち、勘定の属性は、現金との関係によって定義付けられるのである。
なぜならば、勘定の性格は、現金の流れ与える勘定の働きによって決まるからである。そして、勘定の資金の流れに与える働きには、時間が作用する。故に、勘定の性質は、時間の作用によって左右される。
勘定の性質、即ち、勘定の属性が時間に左右されるのは、勘定が期間損益を確立されるために設定された命題だからである。
現金は、取引が成立した時点での貨幣の運動量を示している。取引よって生じる貨幣の運動は、同量の債権と債務を生じさせる。
単位期間内で清算される債権が収益であり、次の単位期間まで繰り越されるする債権が資産である。単位期間内で清算される債務が費用であり、次の単位期間まで繰り越される債務がが負債である。
会計上における時間の作用を決定付けるのは、会計期間の単位である。会計期間の単位によって長期作用と短期作用が区分される。それは取引を類別する際の基準となる。
勘定の性格を決定する要素の一が単位時間である。
資産と費用を区分する基準は、会計期間、即ち、単位時間である。
負債と収益を区分する基準は、資金の調達手段である。
長期的資金の流れと短期的資金の流れとでは、働きに違いが生じる。その働きの違いが勘定の属性を決めるのである。
数学は、理科系の分野だと見なす傾向があるが、文化系の分野、特に、経済にとって数学は必須の学問である。
現代経済は、数学の上に成り立っている。
資本主義制度は、近代会計制度の上に構築された思想である。広義の会計制度には、現金主義会計制度と期間損益主義会計制度の二種類があり、資本主義は、期間損益主義会計制度の上に成り立っている。
現金主義会計制度は単式簿記を基盤として成り立ち、期間損益主義会計制度は複式簿記を基盤として成り立っている。
複式簿記に基づく貨幣経済体制は、高度に数学的社会である。
会計現象とは、任意な現象であり、所与の現象ではない。あくまでも会計現象は人為的な現象なのである。
よく会計や簿記は解りづらいと言われる。なぜ、会計や簿記は解りにくいのか。会計や簿記が解りにくいというのは、会計は仮想上の事象だからである。
会計は、元々、経営実績を報告するために形成された。会計は、投資家に対する報告を目的とした制度なのである。
我々は、利益とは、収益から費用を引いた値と言われると利益の意味を何等かの実体のある物として解釈したつもりになる。それは、現実に「お金」の計算が目の前で為されるからである。しかし、実際には、利益や収益、費用というのは何ら具体性のない抽象的概念なのである。貨幣という物自体が抽象的な指標なのである。
複式簿記は、期間損益を計算する目的によって形成された。それが費用対効果の測定を目的とし、その結果、期間利益、期間損益計算が確立されたのである。
つまり、利益の概念は期間損益上の概念である。
この様な複式簿記の上に構築された会計的空間というのは、高度に数学的な空間、仮想的空間なのである。いわば虚構である。しかし、その仮想的空間での出来事が現実の人々の生活に必要な財を動かしているのである。この点を解明しないと貨幣経済の絡繰りは理解できない。
単式簿記というのは、期首残高に収入を足して支出を引き期末残高を出す方式である。この場合、資金の性格や働きは問題とならない。その為に、費用対効果の計算ができない。むろん、期間利益の計算もできない。
単式簿記に基づく現金主義会計は、現在でも財政や非営利団体、家計などで用いられている。単式簿記の典型は、家計簿である。
また、管理会計、キャッシュフロー会計も現金主義によっている。
注意しなければならないのは、単式簿記による会計と複式簿記による会計とは異質な事象であり、根本的な思想が違うという点である。
故に、現金主義会計制度と期間損益主義会計制度とは、制度的連続性はない。
資本主義の根本となる株式会社会計は、当座企業から始まる。当座企業が前提としたのは当座事業である。当座事業というのは、一回の交易を指して言った。一回の交易とは、一航海で行う貿易のことを指す。
一回一回の航海で事業を清算し、利益の分配をしていたが、度重なるとその都度事業を解散するよりも継続的に事業を行い、一定の期間で損益を計算した方が経済的であることになった。そこから期間損益の思想が生まれたのである。
当座企業の段階では、現金主義と期間損益主義とは未分化である。期間損益主義が確立されるのは、継続企業が成立することによってである。
大前提は、今日の会計制度は、複式簿記を文法とするという事である。
Aの運動や働きに連動してBの運動や働きが変化する場合、AとBとは関係しているという。AとBが集合である場合は関数という。
取引の集合と複式簿記を構成する勘定の集合は連動している。故に、複式簿記は、関数である。
また、複式簿記に基づく会計的現象は、数学的現象である。
会計が対象とする現象は、取引の集合体である。故に、期間損益を確立するためには、先ず取引の認識が前提となる。即ち、取引の定義から始まる。取引の定義は、取引の認識の定義である。
会計は、取引の認識、取引の記録、取引を分解して勘定へ仕訳し、それを勘定毎に転記し、期末に勘定を締めきり、締め切った後、勘定毎に集計し、決算仕訳をして、損益、貸借に分割するという操作によって単位期間の利益を計算する手続である。
即ち、会計とは、関数である。
簿記は、取引の認識により始まる。取引の認識と取引の範囲が複式簿記の原点である。
複式簿記が成立するための大前提は、全ての取引を記録するという点である。会計現象は、記録された取引の集合だとも言える。
取引は、二つの要素、勘定に分解され、借方、貸方の二つの次元に写像される。
取引によって生じる二つの方向の働きとは、一つの方向、即ち、借方の方向は、債権と費用であり、もう一方の方向、即ち、貸方の方向は、債務と収益である。債権と費用は、資金の運用と消費を意味し、債務と収益は資金の調達と売上を意味する。
注意する点は、取引は、取引が成立した時点においては会計上均衡しているという事である。
会計上というのは、複式簿記の文法の上では均衡していることになっているという事である。つまり、会計上の均衡とは、仮定だと言う事である。
複式簿記において貸借は均衡するのではなく。貸借を均衡させるのである。実際は、必ずしも均衡しているとは限らない。あくまでも外見上、或いは、形式的に均衡させているのである。
借方、貸方は、会計上均衡するように設定されているのであり、現実に、貸方、借方の貨幣価値の総和が等しいという保証はない。即ち、借方、貸方の均衡は見かけ上の均衡である。
借方勘定は、具象的な勘定であり、貸方勘定は、抽象的な勘定である。具象的というのは、財を基盤とし、抽象的というのは貨幣、資金を基盤としているという事である。又、貸方は基本的に具象的であるという点から正の勘定であり、借方は、負の勘定である。
借方は、実質的勘定であり、貸方は名目的勘定である。実質勘定とは、財に根ざし、名目勘定は、貨幣に根ざす。
財の貨幣価値は相場によって決まり、債務の貨幣価値は契約によって決まる。債権は財を基として、債務は約定を基とする。
取引上、一つの勘定に対して必ず同量の相殺勘定が働いている事になる。
相殺勘定は内部取引を派生させる。すなわち、会計は外部取引と内部取引との相互作用の上に成り立っている。内部取引というのは仮想的取引である。
個々の勘定科目には正の位置と負の位置が定まっている。そして、個々の勘定科目の残高は常に零を含む正の自然数である。
仕訳上は、同じ勘定科目間でしか加減計算はできない。残高が問題となる。
簿記は残高主義である。
複式簿記の前提は、取引のに方向性と非対称性である。即ち、複式簿記では、取引は、取引が成立した時点において二方向の働きに分解し、非対称の要素に仕訳、分類するという事である。これは取り決めであって自然法則のような規則とは違う。
一つの方向の勘定は、反対方向の同量の勘定と一組になって成り立っている。故に、借方、貸方の残高は常に一致することになる。
取引の非対称性が問題となるのである。取引は、相反する方向で同量の勘定によって成り立っていながら、個々の勘定を構成する内容、要素が非対称なのである。しかも、取引を構成する個々の勘定は各々固有の働きをする。それが会計現象を複雑にしているのである。
しかし、取引の最終的な形は、現金だという事である。言い換えると現金化の過程が会計の基本的な経路だと言える。
取引は、貨幣価値を実現すると同時に、同時に、それと同量の債権と債務を成立させる。或いは、財と貨幣の流れを生じさせる。貨幣は、会計主体を経由して流れ出すのである。故に、資産も負債の残存価値に過ぎない。貨幣ではないのである。
会計主体の活動は、この資金の流れによって生み出される。会計主体とは、資金の流れによって動く観念的仕組みなのである。
そして、会計現象とは数学的現象なのである。
総資産、総資本の増加は、運用側への資金の流れを促す。総資産、総資本の収縮は回収側への資金の流れを生み出す。
財の残存価値を資産と言い。財の費消を費用という。現金の調達の中で、借入による現金の調達を負債とし、売上による現金の調達を収益とする。元金、原資、利益の蓄積を資本という。
先ず資金を調達する。その資金を資産に置き換える。次ぎに資産を費用に変換する。そして、費用を収益に転換する過程で利益が生じる。その利益を資本に蓄積する。これが正の経営循環である。
今日の株式会社は、経営と資本、労働者、即ち、経営権と所有権、労働権が分離している。即ち、資本と、経営者と、労働者が分離した体制である。この事によって株式会社の主体性が稀薄となる傾向がある。
経済的価値は、正と負が常に一致している。経済的価値は、会計上は、正と負が同時に発生する。
会計上、取引が生みだした価値は、表面的には、均衡していることを前提とする。即ち、差引0である。つまり、調達した資金と運用した資金は、結果的に無になるように予め会計上は設定されているのである。
複式簿記というのは、取引が均衡するように設定されているのである。そして、取引が均衡なるように設定されていることが自由主義経済の在り方を根本的に定めているのである。
取引を区分する尺度で重要な役割を果たしているのが単位時間だと言う事である。
期間損益を確定するには、決算仕訳が重要な意義を持ってくる。なぜならば、決算仕訳によって費用を按分するからである。
決算仕訳は、期間損益を確定するための手続、操作である。最も期間損益の思想が鮮明となる部分である。決算仕訳は、主として償却資産、在庫、繰延勘定、そして、評価勘定の処理が重点となる。
減価償却という思想によって期間損益は確立された。即ち、償却の在り方は、期間損益の在り方を規定するのである。
複式簿記は、調達側と運用側が、常に均衡していることを前提としている。考えてみれば不思議な構造をしている。調達された資金は、増えもせず減りもしない。
つまり、単位期間にあげた利益は、その期が終わったら清算をしてしまうことが前提なのである。
この様な前提に立てば、収益が減少すれば忽ち均衡が崩れる。資金を蓄えておく余地がないのである。
会計主体を動かしている原動力は、資金だという事である。
会計主体を動かしているのは、資金であるが、手持ち現金の量と総資産、総資本の総量とは直接関係があるわけではない。企業の手持ち現金の量は意外と少ないのであり、また、企業経営は、手持ち現金の量を少なくした方が効率的なのである。
又、手持ち現金の量と損益は連動していない。
期間損益と現金収支とは別の物であると言うことである。
資本も残存価値に過ぎない。いくら見かけ上の資本があっても換金されない限りは、経営資源にはならないのである。
だから、いくら過去に利益をあげていたとしても収益が悪化すれば途端に苦況に陥るのである。収益が悪化すると円滑な資金の循環が阻害されるからである。
資本主義体制というのは、貨幣が常に循環していることを前提とした体制なのである。貨幣が循環しなくなると経済を構成する主体が機能しなくなるのである。
会計制度は経営実績の報告を目的とした制度であるが、必ずしも、実体を反映しているとは限らない。表面に現れている数値は、会計の規則に基づいて計算された数値であり、それは会計制度上においてしか成立しない見かけ上の数値である。
経営や投資で重要なのは、また、経済を考える上で重要なのは、見かけ上の貨幣価値ではなく、資金が流れる量と方向なのである。
一億円を借り入れて設備投資をした場合を想定する。一億円は、貸方に一億円と記載されると同時に、借入に、借入金として一億円が記載される。借り入れた現金は、設備代金として支払われる。即ち、現金は、入金されたら、すぐに出金されるのである。
お金は、入ったら、すぐに出ていく物なのである。お金が流れたとに財と債務が残される。財は資産となり、資産は残存価値であり、潜在的価値を形成する。
現金は、通過するだけである。だから、貨幣価値で表示されているとしてもお金があるわけではない。例えば資本金と言ってもそれは、現実に「お金」があるわけではない。資本金というのは、元手を表した象徴的な数値なのである。
企業には、思っている程、金は残らない。
企業基盤は、一般に考えられているよりも脆弱なのである。
企業基盤が脆弱である原因の一つに、企業の機関化がある。即ち企業の主体性が希薄化していることである。企業の主体性が希薄化することによって企業の自律性や継続性、また、求心力が失われつつあるのである。
決算処理が終わったら、次は利益処分である。この利益処分の仕方に資本主義の特徴はよく現れている。利益処分とは、利益の分配を受ける物に対する配分を決める事である。そして、利益の分配を受ける権利があるのが、株主と経営者、そして、国家、及び、公共団体である。会社にも、社員にも利益配分を受ける権利はない。利益配分を受け取る権利は会計主体の外にあるのである。それが今日の企業の体質を脆弱にしているのである。
もう一つ重要なのは、納税額は利益処分から導き出されるという事である。即ち、税は費用と見なされず。配当や役員報酬と同じ次元で捉えられているという事である。そして、その按分が大きいという点である。
会計主体を定義する上で鍵を握るのが内と外との範囲が問題である。
特に、資本が内と外どこに帰属するかによって会計主体や経営主体、延(ひい)ては、会計目的の在り方にも重大な影響を与える。
企業は、共同体なのか、手段、道具なのかである。
機関化したら利益を企業内部に蓄積する動機、利点がなくなるからである。つまり、利益は、外部に帰属するため、外部の人間にとって利益は、その期が終了した時点で分配された方がいいことになる。
利益が上がった時点で経営者は報酬をもらい、株主は、配当をもらい、徴税者は、税金を徴収する。それが合理的な選択なのである。
高額な報酬を問題とするが、個人の所得を増やすのは合理的選択の一つである事を忘れてはならない。問題があるとしたら、合理的選択肢の一つになり得るという点である。企業にとって合理的選択肢になり得たとしても社会正義、分配の公正から見て妥当かというと、それは違う。弊害が多い。
合理的選択肢になりえるのは、個人所得の根本思想が現金主義によるからである。又、いくら企業が利益をあげても、機関化された経営主体では、蓄えておく動機も、手段もないのである。
そして短期的な利益のみを企業は、追い求め、将来に対する投資を怠るようになる。その結果、企業は涸れてしまうのである。
現代でも、大企業は、労働者や社会から搾取していると錯覚している者がいるが、大企業こそ搾取されているのである。
企業にとって利益が蓄積できないとなると、誰のための、何のための利益かと言う事になる。経営者は、単に資金を調達するためだけの見かけ上の利益のみを追求するようになる。そうなれば経営の継続性が危うくなるのは、必然的結果である。しかも、得をする者は誰もいなくなる。
企業が有効に機能し得ない原因の一つは、経営目的が個人の欲望を充たす動機に限定され、公の目的が見失われていることにある。経営目的とは、利益の根源である。つまり、利益本来の意義が忘れられているからである。利益をあげる要因は、個人的欲望の充足だけにあるわけではない。公的な目的による部分が大きいのである。
いくら合理的な選択肢として巨額の報酬を得ることが可能だとしても経済の目的からすれば逸脱しているし、また、その様な勝手を許す仕組みがおかしいのである。その様な経済の仕組みは、人間を堕落させるだけである。人間を堕落させるような仕組みは明らかに、経済的合理性を欠いている。
それは経営目的が経済の本来の目的に根ざしていないからである。利益の追求は、経済の目的を実現するための手段である。経済、本来の目的は、労働と分配にある。会計主体は、経済の目的を実現するための手段であり、労働と分配を実現するための仕組みである。会計主体は、利益をあげるために存在しているわけではない。利益を目的としたら、会計主体は、利益をあげると言う目的の為に利益をあげることになる。
利益をあげても当然その利益の配分に与(あずか)るべき人に渡るような仕組みになっていないのである。
企業の共同体から機関化というのは、企業を成立させている人間関係が有機的結合から、機械的結合に変質することを意味する。つまり、企業から人間性か失われているのである。それが企業に対する人間的な感情を失わせる結果を招いている。
愛社精神など死語になりつつある。企業や組織に対する忠誠心は失われてしまったのである。その為に、企業が危機的状況に陥った時、企業も、経営者も、社員も、主体的な行動がとれなくなりつつあるのである。まるで、朽ち木が倒れるように、歴史や伝統がある企業が倒れていく。つまり、企業の継続性が失われつつあるのである。
企業の在り方を考える上で、資本の在処が、企業内部にあるのか、外部にあるのか、又、どの様な動機に基づいて資本を握るのかが重要になる。資本の在処は、経営主体の在処だからである。
重要なことは、企業の主体はどこにあるのかという点である。そこで資本のありどころが問題となる。資本は、内部勘定なのか、外部勘定なのか、それが資本を定義する上で重要な意味を持つ。資本を握る者が会計主体の内部にいるのか、外部にいるのかという意味である。
即ち、資本が帰属するところによって会計主体に質的な違いがある。資本が帰属するところは、経営権が帰属するところでもあり、会計主体の実質的所有者となるからである。
資本の帰属するところとしては、第一に、株主がある。第二に、経営者、第三に、何等かの法人や組織、第四に、国家、或いは、公共団体、第五に、社員、又は、従業員、第六に、組合、第七に、経営者、社員、組合が一体となった体制が考えられる。そして、この資本に対する考え方が資本主義を規定するのである。
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2009.12.20 Keiichirou Koyano