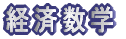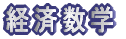一は、全体でもあり、部分でもある。
唯一の一でもあり、万物の一部の一でもある。
存在は唯一。自分は一人。人生は、一つ。
しかし、広大な宇宙から見れば自分なんてちっぽけな存在に過ぎない。自分は、社会の一部である。
選べる物は限りなくあっても、実際に選べる物は一つしかない。信じられるものは一つ。なぜならば自分は唯一の存在だからである。
人生は、一路。分かれ道は多くても進むべき道は一つしかない。
個としての一。分かたれた一。切り出された一。独立した一。特別な一。
単位としての一。定められた一。一定の一。一定の長さの一。一定の時間の長さの一。それは、単位時間であり、単位期間である。
一歩一歩。一つ一つ。一個一個。
一刻一刻。一瞬一瞬に、過ぎ去っていく時間。
時間と時刻。連続した時間と分離された時刻。
期間と定刻。それは経済の基本単位を形成する。
時は、連続している。変化は連続しているからである。しかし、連続している時間に対する認識は、時間を連続した流れとする認識と分離した点、時刻として認識する二つの認識の仕方がある。時間は連続時間であり、時刻は、離散時刻である。
会計上では、連続時間による損益と離散時刻による貸借の両面へ経営の実体を写像する。
過去。現在。未来。
そして、今。
取り返すことのできない時。失われた時間。後戻りできない時間。やり直すことができない時間。
時間は、不可逆である。
時間は、方向性を持つ量である。
時には、前後がある。時には、順番がある。時には、新旧がある。
仕事は、作業の順序集合である。物事には順序がある。
最近の若い者は、子供を作って結婚をして親の承諾を得ようとする。それは話の順番が逆である。最初に親の承諾を得て、結婚をして、子を成すのである。
組織的仕事は、決定があって指示があってはじめて作業にかかれる。決断が始まりである。結果が出てから決断をするわけではない。因果応報である。
だから、手順、手続、段取りが大切なのである。
この世では、人は生まれて死ぬのである。死んで生まれるわけではない。
生病老死。
老いは残酷である。若く華やかな時は、瞬く間の内に過ぎ去り、いくら後悔をしても取り替えせはしない。若く力が漲っている時は、怖い物知らずで、自分一人で何でもできるように傲慢になるが、老いて他人を思いやることができるようになった時は、人の助けがなければ生きいけない。
人の一生は、時間の性格に関わる。時は無情である。時刻は、数直線を形成する。一瞬に普遍があり、時と時の間に無限がある。時空は、今、実現し、そして、過ぎ去っていくのである。万物は流転する。諸行無常。
哀しいことに、年をとればとるほど自分の過ちを認められなくなる。それまでの自分を総て否定されるようで、怖ろしくなるからである。
若いうちは、やり直しがきくが、年をとるとやり直すことができないと思い込むからである。
しかし、だからといって何時までも意地を張っているべきではない。あやまちは、あやまちとして潔く認めるべきなのである。
そうしなければ何も改まらないのである。新しい人生が始まらないのである。肉体は老い衰えても心はいつも新鮮になれる。それが時間の持つ宿命である。
時間は変化の単位である。
時間は、変化の単位である。変化は、運動である。運動は時間の関数である。時間が経済的価値を生めば、経済的運動は、経済的価値を派生させる。即ち、経済的価値は、変化によって生じ、時間がもたらすのである。
損益は、運動量を示し、貸借は経済量の位置エネルギーを表している。
経済量は、単位時間内における単位量と回転数によって決まる。
貸借は、調達した資金の残高を意味する。それに対して、費用というのは、単位期間に費消した貨幣価値の量を言う。費消するとは分配を意味する。
仕事量は、運動量と距離の積である。
貨幣の運動量は、貨幣の流量と働きの積である。
経済的距離は、時間的隔たりである。それは、単位期間に対する貨幣の回転数として現れる。
経済量の総量は、通貨量×回転数である。
運動は、変位、速度、加速度によって表現できる。
変位、速度、加速度は、時間と距離の関数である。
距離とは、物理的空間の距離のみを指すわけではなく。量的な隔たり、幅を言う。物理的空間以外の距離には、価格、仕事、熱等がある。
静止した状態とは、時間が陰に作用している状態を言う。
速度は、連続した外延量である。
貨幣的距離は、貨幣単位×数量によって求められる。
金利は貨幣単位における加速度である。
等速運動時において基本となる速度と加速時において基本となる速度は次元を異にしている。掛け算は、次元を変換する。
運動の型には、第一に、放物線運動型、第二に、終端速度型、第三に、単振動型の三つがある。
そして、これらの運動の背後には、直線運動と円運動が隠されている。
経済は仕組みが重要である。経済の仕組みは人工的仕組みである。人工的仕組みは設計が必要である。経済の仕組みは、目的にそって設計される。経済の仕組みには目的がある。経済の仕組みは合目的的な仕組みである。それなのに、現代の経済の仕組みは、目的を明らかにされていない。
目的に変わってあるのは、神の意志といった曖昧な概念にすぎない。経済は、人間の営みである。それは人為の世界である。人為の世界の過ちを神の責に帰すのは怖れ多いことである。それでは人間は救われない。神事は神に、人事は人に帰すべきである。
飛行機は、速度だけを目的としているわけではない。飛行機が速度だけを追求していたら、今日のような飛行機産業の発展はないであろう。
経済の目的は、人を生かすことにある。現代の経済体制は、無目的である。ただ、速度だけを追求する飛行機のような設計しかされていない。だから住み難いのである。
時間は、数列である。複数の時間の数列は、構造を形成する。
拍子。旋律。和音。
音楽は、音と時間の数列が醸し出す構造と調和である。
時は金なり。
「お金」即ち、表象貨幣は、無次元の量である。実体はない。
貨幣価値は、観念の所産である。観念は認識によって生じる。つまり、貨幣価値は、認識上に派生する価値である。
自己は、認識主体であると伴に、間接的認識対象である。故に、認識上必要性から作用反作用が生じる。自己を対象に写像し、その写像を認識する事によって間接的に自己の意識を人間は知るのである。
その媒介として貨幣が生じる。いわば貨幣は鏡である。貨幣空間と現実の空間は、鏡像対象の関係にある。貨幣は、無次元の量である。実体はない。実体がないことによって貨幣は機能する。貨幣が実体を持つと、経済は歪む。なぜならば、貨幣は、経済の実体を写し出す鏡だからである。鏡に意志はない。
鏡が歪めば、経済も歪んでしまう。それは、実体の問題ではなく。鏡の問題である。
物流と貨幣の流れは、反対方向に流れる。それが、経済の作用反作用を起こす。即ち、物の流れと貨幣の流れは、反対方向の働きを持つ。
物の正の働きに対して、貨幣は、負の働きをする。それが債権、債務、貸し借りの形として現れる。
貨幣の発行には必ず負の働きが伴う。即ち、貨幣の発行は、何等かの公的債務を発生させる。それは、貨幣の働きは、債権を発生させるからである。公的債務が生じると言う事は、公的債権が生じることでもある。
即ち、貨幣の運動によって同量の債権と債務が発生する。債権と債務は決済によって解消される。
負の働きは、貨幣の働きを有効にするために不可欠な働きであり、悪質な働きではない。
貨幣の流れる方向は、負の部分の働きに負うところが大きい。負の部分というのは、資金の調達と回収に深く関わっているからである。負の部分の働きを解析しない限り、資金の流れる方向や力を明らかにすることはできない。負を文字通り、消極的な働き、又、否定的な働きとばかり考えていたら、貨幣の持つ働きや力を積極的に、肯定的に活用することは不可能である。
負債の働きを規制する要素は、長期、短期という周期と流動性である。
国債を公的な負債だけだと見ると間違う。国債は、公的債権も同時に生み出しているのである。それが貨幣発行益である。貨幣発行益の働きを明らかにしなければ、貨幣制度の働きの全貌を理解することは出来にない。国家の長期的資金需要の多くは、税収ではなく。貨幣発行に伴って発生する貨幣発行益(シニョレッジ)によってもたらされている。
硬貨を発行する場合、金貨と銅貨どちらが儲かるか。それは銅貨である。銅貨の方が材料費が安いからである。ならば紙幣と金貨では銅貨。紙幣は発行した時に莫大な利益が生じる。即ち、それが公的債権なのである。この公的債権と公的債務が同時に発生していることを忘れてはならない。税収というのは、この公的債務と債権の回収に他ならないのである。そして、税収と公共投資とは区別して考える必要がある。回収した資金の中からどれだけ再投資すべきかの問題である。問題なのは、公的債権、債務をどの水準に収束させるかなのである。
貨幣経済は、貨幣によって正の働きと負の働きがある。貨幣経済は、その均衡と調和によって保たれる。貨幣経済の均衡を保つのは、市場の働きである。市場は取引によって成り立っている。故に、取引は均衡する。
取引が均衡するから、複式簿記上の借方、貸方も均衡する。
単位貨幣間の関係は表裏をなす。即ち、為替の問題は、単位貨幣の濃度の問題である。
現代の経済は、時間が重要な要素の一つになっている。経済は時間の関数だとも言える。時間の経過に伴ってどの様にして価値が形成されていくかが重要となるのである。
期間損益は会計的概念である。会計には、現金主義と期間損益主義がある。
財政は、民間の基準である期間損益に基づいておらず、現金主義に基づいている。その為に、会計と財政との制度的整合性はとられていない。
会計上の規律が財政上に於いて守られないのは、財政が会計制度に従っていないからである。
民間に於いて不正と見なされる行為も財政に於いては不正とは見なされない。民間企業が破産すれば、責任を問われるのに対して、財政や公益事業に於いて破綻しても責任を問われることはない。それは、公益事業は、営利を目的としていないと言う理由である。しかし、これは欺瞞である。公益事業でも働く者は事業によって報酬を得ているのである。
これまで資本主義経済は、都合良く現金主義と損益主義を使い分けてきた。それが混乱を引き起こす原因となっているのである。
民間企業と政府との決定的違いは、権力の有無である。
民間企業では犯罪になることでも、政府がやれば犯罪どころか、功労者になる。結局、財政の規律が保ちにくいのは、外部から監視が公益事業には利きにくいからである。財政も監査されてしかるべきであり、又、経営責任も問われるべきなのである。
期間損益というのは貸し手の必要性から生まれたものである。使い手が必要としているのは、現金収支、即ち、現金主義である。事業は、金さえ廻れば存続可能なのである。そこに落とし穴が潜んでいる。
現金主義は、期間という概念に拘束されていない。なぜならば、期間によって数値が変わるような勘定科目を設定する必要がないからである。
取引の都度、現金の出納を記録すればいいのである。それが単式簿記である。単式簿記の基本は、現金出納帳である。
単位期間と言っても、単に一定は期間における現金残高を計算するための目安に過ぎない。
それに対し、期間損益では、期間は、あらゆる勘定の基礎となる単位である。それは、期間によって勘定科目の性格が異なってくるからである。この点を理解しないと現在の資本主義やや自由主義経済を理解することはできない。
経済は拡大均衡と縮小均衡を繰り返す。拡大均衡だけを前提とすれば財政が破綻するのは必然的な帰結である。
拡大均衡と縮小均衡は、一定の波動となる。波動には、短期の周期の波動と中期、長期の波動がある。
経済変動、即ち、インフレーションやデフレーションは、時間価値の変動によって引き起こされる。時間価値を構成する要素は、金利、所得、物価、地価等がある。時間価値の働き、長期、短期によって差がある。また、社会全体に一様に働く作用と社会を構成する要素に個別に働く作用がある。
例えば金利は、社会全般に一様にかかる。それに対して、所得は、個人所得に及ぼす影響以外に、雇用等及ぼす影響がある。また、物価は、財によって時間価値の変動に差が生じる。
時間価値がどの様な作用を社会や個々の要素に及ぼすかを考慮して経済政策は立てられる必要がある。
現代経済は、変化を前提としている。変化とは動きである。動きによって個の位置を絶えず調整することによって現代経済は、成立している。変化がなくなれば、社会全体が硬直化し、環境や状況の変化に対応できなくなる。そして、現代の市場経済は、市場の拡大、成長、発展、上昇を前提としている。なぜならば、費用が下方硬直的だからである。
現代の日本はゼロ金利時代が長く続いている。ゼロ金利時代が長く続くと、時間価値が作用しなくなる。金利はゼロでも、生活にかかる経費は、上昇する。人件費も上昇する。それは、家計や企業利益を圧迫し、景気の頭を抑える。財政赤字における一番の問題は、国債の残高が蓄積されは、金利を硬直的にすることにある。
期間というのは、一種の思想である。自明なものではない。
時間価値は、期間が定まることによって成立する。一定の時間の長さで区切って価値を特定する。
時間は連続量である。数量は連続量である。貨幣は分離量である。
時間も数量も外延量であり、貨幣は内包量である。
期間は、始点と終点を前提とする。
時間は、連続量であり、時刻は、分離量である。
時間は外延的であり、時刻は内包的である。
損益は時間により、貸借は、時刻による。
時間を時刻で切断としたのが、期間損益である。
会計空間は、ベクトル空間である。即ち、会計運動は、量と方向性があり、初期条件、初期の位置が重要な働きをする。
会計は、代数和の世界である。そして、同類項をまとめる事によって成り立っている。
会計は、残高主義、加算主義である。
会計は、時間の関数の関数である。
期間は、時間の単位である。
期間損益における成果を測る基準には、利子と利益の二つ在り方がある。
利益というのは、分け前、分配を意味する。
金利とは、時間的価値を意味する。
金利と利益の力関係によって資金の流れ方向は変わる。金利の力が強ければ、資金は回収の側に、即ち、返済の側に流れ、利益の力が強ければ、資金は、投資の側に流れる。
なぜならば、金利は、負債が費用に転じる過程で生じ、利益は、資産が収益に転じる過程で生じるからである。
その意味で金利と利益の力関係を見極めることは、景気対策を立てる上で決定的な要因となる。
単位期間を設定することによって時間の働きを陰にすることができる。
時間が陰に作用した場合、金利の働きは単利となり、陽に作用すると福利になる。
会計は、経営主体に対する入力と出力からなる。
経営主体には、領域があり、境界線を境にして内と外に分かれる。
経営主体は、取引を通じて経済活動をする。経営主体が行う取引には、内部取引と外部取引がある。
内部取引は、内部に対して対称であり、外部取引は、外部に対して対称である。そして、内部取引と外部取引は常に会計上均衡している。
内部取引と外部取引とは、鏡像対称関係にある。この様な鏡像対称によって複式簿記に表される取引の作用反作用の関係が成立する。
経営主体は、人的な場、物的場、貨幣的場が階層的に重なっている。そして、それぞれの場は、人的構造、物的構造、貨幣的構造を形成する。
経済の実体は、生産、在庫、消費の均衡をとることであり、又、労働と分配を結び付けることである。その仲介をするのが貨幣であり、その意味で貨幣は重要なのである。
生産には、生産手段と原材料と労力が必要となる。生産手段は、初期に投資が集中し、操業が始まると潜在的な費用になる。原材料と労力は、短期的な支出を形成する。実際の支出は、支払方法に関わる。この様な事情によって資金には、短期的長期手働きの差が生じる。
即ち、経営主体に対する資金の働きには、長期的周期の働きと短期的周期の働きがある。
損益と貸借を区分する基準は単位時間である。
期間損益は、貨幣の長期的働きと短期的働きを区分したものである。
長期的な働きは、ストックを形成し、短期的な資金の運動は、フローとなる。長期的働きと、短期的運動は、必ずしも一致した動きをするとは限らない。それぞれが独自の働きや動きをする。その働きや動きの意味を読み違うと適切な対応ができなくなる。
物価の上昇局面では、負債は、軽減される方向に、資産には負荷がかかるように働き。物価の下降局面では、負債の負担は重くなり、資産の流動性は高まる。
バブルという現象は、フローの部分は、通常の動きをしているのに対してストックの部分が異常に高騰している現象である。ストックの中でも、不動産や金融資産の部分に顕著に現れる場合が多い。また、特定の部分だけに現れることもある。ストックの部分とフローの部分が乖離することによって不整合、不安定な状態になり、格差が広がって景気が暴走し、制御不能に陥るのである。
長期的な場というのは、必ずしも現金の動きを伴っているとは限らない。過去の現金取引の名残や返済義務のような部分が多分に含まれている。それらが、債権や債務を形成し、資金の流れる方向を決定付けている。
長期と短期の区分によって期間損益主義は成り立っている。区分の基準は単位期間である。
長期的資金の働きは、債権と債務を形成し、短期的資金の流れは、収益と費用を成立させる。実際の経済単位の働きは資金の収支によって動かされる。経済単位の働きは、労働と分配である。
貨幣は、資源化されることによって資金となる。
経済上計上される貨幣価値の量と市場に流通する資金の量とは一致しない。
期間損益というのは、費用対効果の関係を明確にすることによって資金の流れを円滑にする目的によって形成された。故に、期間損益を真に有効たらしめるためには、貨幣の流れる方向と損益の関係を明らかにする必要がある。
その為に、近年キャッシュフローが重視されてきたのである。しかし、現状を見るとキャッシュフローを明らかにすることの本当の意義が理解されているわけではなさそうである。それがキャッシュフロー万能の様な誤解や、又、現金収支、資金繰りとキャッシュフロートを混同する様な混乱を招いている。
キャッシュフローを重視するのは解るが、キャッシュフローが悪いからと言って資金の供給を止めることは、血行が悪いと言って止血するようなもので、収益を改善するどころか瀕死の病人にとどめを刺す行為に等しい。それは、過失ではなく。犯罪である。
現金収支は、現実の資金の動きを記録したものであり、資金繰りは、資金の過不足を管理するための帳票である。
資金の実際の動きを知りたければ試算表を解析した方が手っ取り早い。
キャッシュフローというのは、資金の働きによって資金の流れを分類したものである。
資金の働きをキャッシュフローは、営業と投資と財務キャッシュフローに分類する。
資産は、生産手段、貨幣は交換手段、所得は、分配手段である。投資は、資産に関わる資金の流れを形成し、貨幣は、財務に関わる資金の流れを形成し、所得は、分配に関わる資金の流れを形成する。
投資はキャッシュフロー、生産手段に対して支払われる資金の流れである。
財務キャッシュフローが表すのは、取引や経営に必要な資金の調達と貯蔵、そして、返済(回収)として活用される資金の流れである。
営業は、労働と分配に対する資金の流れである。
投資は、基本的に長期的資金の流れを表す。又、財務は、中期的資金の流れを表し、営業キャッシュフローは、短期的な資金の流れを表す。
投資や財務と言った長中期的資金の流れは、会計では、損益上に表されない仕組みになっている。しかし、これら長期的資金の流れは、経済の底流の資金の流れる方向を決定付けている。
減価償却費も借入金の返済計画は、有限数列である。減価償却費や借入金の返済は、計画数列の典型である。
減価償却の計算方法には、第一に年数法、第二に、比例法がある。第一の年数法には、定額法と定率法の二つがある。定率法は、第一に、逓減法、第二に、逓増法からなる。更に、逓減法は、定率法と級数法がある。そして、逓増法は、償却基金法を言う。比例法には、生産高比例法と時間比例法などがある。
この様に、減価償却の手段は多様であり、その選択は恣意的である。
減価償却は何に基づくかは、目的によって違ってくる。減価償却費の設定は、会計上の目的から生じている。会計上の目的とは、投資家や債権者に対する説明責任である。投資家や債権者は、現金収支だけでは経営の実態が把握しにくい為に、期間利益を計算することを求めたのである。しかし、その結果、利益だけが重視されるようになった。
赤字、即ち、損失が発生した時、問題は、利益を上げられない原因なのである。その原因が一時的現象に依拠しているのか、構造的な問題なのかで、処方箋も違ってくる。黒字か、赤字かが重要なのではない。問題は、病根なのである。殺すことではなく。生かすことを考えるべきなのである。重要なのは、事業を継続すべきか、否かの判断である。その場合、単に、会計上に表れた数字だけでなく。その経営主体が果たしている社会的責任、例えば、事業が果たしているの社会的役割や雇用などの質的な問題も勘案する必要がある。
減価償却費は、期間損益を計算する上での前提となる科目である。故に、減価償却費は期間損益を計算する目的や動機から設定されるべきものである。
しかし、現実には、決算対策として利用されている場合が多い。つまり、利益を出すための方便に減価償却の計算方法が使われるのが実情である。
その結果、期間損益の目的が見失われがちになっている。
減価償却の計算方法というのは、期間損益を計算する上で根幹となる部分である。故に、減価償却の計算方法は、期間損益に対して決定的な働きをする。
ところがその計算方法が実際にはご都合主義によって決められている。それが問題なのである。選択肢を与えることの是非の前に、その根拠が曖昧なのである。しかも、その様に重要な決定が無作為にされるといることが問題なのである。
その結果に、期間損益の意義が失われつつある。利益を算出されることが優先され、損益の原因がおざなりにされているのである。その為に、外見だけ取り繕って問題は先送りされる傾向が強くなっている。
経営実績が悪化した時、重要なのは、経営者の倫理や技術、知識不足、経験不足といった経営上の問題なのか、為替や原油価格の高騰、物価、地価の下落と言った経済環境、状況の問題なのか、過当競争や市場の過飽和、商品のライフサイクル、人件費の内外格差と言った構造的問題が潜んでいるかである。
経営の実体と減価償却との関係を明らかにしようとした場合、減価償却の数列と、借入金の返済、収益構造、資産構造と言った他の数列との相関関係を明らかにする必要がある。
例えば、減価償却に関わる科目には、利益、納税額、借入金の元本の返済額、更新資金、保守修繕費、保険料等があるが、それらの科目のどの部分が減価償却費とどの様な関わりがあり、どの様な働きがあるかを知る事である。
減価償却の計算方法は、期間損益を計算する意義に関わる問題である。つまり、期間損益の本質を表している。故に、減価償却の実体は、現在の自由経済の実体を現しているとも言える。
どの様な計算方法が妥当なのかではなく。なぜ、その計算方法を選択したかの動機が問題のである。
減価償却は、期間損益と現金主義、即ち、資金の流れとを変換する操作に深く関わっている。減価償却の有り様一つで利益の額は大きく左右される。そして、それは資金の流れにも重大な影響を与えるのである。
貨幣は、交換手段である。
個人は、消費者であると同時に、労働者である。
経済制度の単位は、国家である。一つの経済圏の範囲は、国境によって画定されている。故に、一つの経済圏を成立させている個人の単位は、国民である。
市場は、市場経済を前提としている経済体制を構成する経済の仕組みの部品、要素の一つである。
市場経済は、生活、即ち、生きていく為に必要な物資は、市場から調達する事で成り立っている。
市場から、必要な物資を貨幣を用いて調達する行為を取引という。
市場経済下において国民が必要な物資を市場から調達する手段は、交換である。その交換に必要な媒体が貨幣である。
この様な、市場経済が成り立つためには、交換手段である貨幣が全ての国民に行き渡っている必要がある。
つまり、貨幣経済が成り立つためには、交換手段である貨幣が所得という形で国民に行き渡っている必要がある。それも単に行き渡っているだけでなく。継続的に分配される必要がある。即ち、供給され続ける必要がある。
また、所得が消費に連なるためには、貨幣が供給されているだけでは消費が一時的な行為で終わってしまう。所得が、消費に連なるためには、交換手段である貨幣だけでなく、動機が必要なのである。故に、景気浮揚策は、消費者の動機を刺激する必要があるのである。単にお金をばらまくだけの対策は、愚策である。
交換手段である貨幣は、消費者である個人に所得として分配される。所得は、何等かの価値を持つ対象の対価として支払われる。対価には何等かの実体を持った代償が必要とされる。
所得には、人を根源とする所得、即ち、人的所得と物を根源とする所得、即ち、物的所得と、金を根源とする所得貨幣的所得がある。人的所得の根源は、労働であり、物的所得の典型は、地代家賃であり、貨幣的所得の根源は、金利である。
全ての国民が所有する代償物は、自己の肉体、即ち、労働である。故に、全ての所得の源泉は、労働に求められるべきだというのが、今日の経済思想の大前提となりつつある。問題は、不労所得である。そして、労働をいかに定義し、評価するかである。
現代の自由主義経済では、消費者が受け取る金利や地代家賃には制限が加えられるのが常である。
金利や地代、家賃に対する制限は、物的所有権や貨幣的所有権から発生する所得は制限されるべきであり、所得の源泉は労働に求められるべきだという自由経済思想に基づいている。この思想は、社会主義にも共通している。社会主義は、更に、所有そのものにも制限を加えようとする。必然的に不労所得は制限を受けることとなる。
貨幣経済、市場経済を基盤とする自由経済体制では、働かなければ、生活ができない仕組みになっているのである。それは、貨幣の循環が社会を動かす原動力であり、貨幣が循環しなければ、市場は成り立たなくなるからである。貨幣経済下では、貨幣は貯めているだけでは、効用を発揮しない。効用が発揮できないような仕組みになっているのである。
だから、所得の偏りは、貨幣経済を破綻させる原因となるのである。
貨幣経済では、総て最後は現金化される事によって決済される。
そして、最終的には、消費と結びつくことによって完結するのである。その消費に結び付ける貨幣の働きの最終手段が所得である。
労働の対価として所得が支払われ、それが、消費と貯蓄にまわされる事によって貨幣は循環する。所得は、労働の質と量に対する対価として支払われる。
故に、自由経済体制では、労働の場が確保されることが絶対的前提となるのである。
そして、消費は収益に、貯蓄は投資に、環流される。
最終的には、経済は、所得の問題に還元される。そして、所得の問題は、労働の分配をいかに均衡させるかの問題であり、労働と分配を均衡させるためには、生産と消費、そして、貯蓄をどの様に調整するかの問題となる。
所得は、収益と費用、費用対効果という関係からも導き出される。所得は、収益でもあり、費用でもあるからである。
飛行機や鉄道、船といった交通機関は、旅客が居なければ成り立たない。百人乗り飛行機は、満席であろうと、十人しか旅客がいなかろうとかかる費用に大差はないのである。ならば、なるべく多くの旅客を乗せた方が効率的なのである。
問題は、価格と所得の釣り合いなのである。飛行機を利用したいと思えるような価格の設定と、飛行機を利用できるだけの所得がなければ飛行機を利用する者は増えない。その意味で、一定の水準の所得層の存在がなければ航空会社の採算は保たれないのである。かといって無原則に所得を振りまくわけにはいかない。そんなことをしたら、貨幣の供給量を制御する事ができなくなるからである。所得を分配するためには、所得に見合った労働を前提としなければならない。
つまり、所得対策こそ最終手段であり、それは所得の裏付けとなる労働を維持することなのである。
所得が最終手段であり、雇用が重視されなければならない事態なのに、費用対効果ばかりが優先されている。それが市場原理主義者の錯誤である。経済効率と、経営効率とを同一視していることが原因なのである。
経済の本質は、労働と分配にあるのである。



このホームページはリンク・フリーです
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures
belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout
permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2010.4.30 Keiichirou Koyano