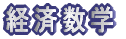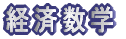日本でも江戸時代までは、税は物納だったのである。貨幣は、補助的、或いは、代用的初段に過ぎなかった。その貨幣も、鋳造貨幣であり、貨幣その物が物としての価値を有していて、紙幣のような表象貨幣ではなかったのである。この点は、重要である。
江戸時代では、現在の政府の相当する江戸幕府は、独自に生産的部分を持ち、君主である将軍家は、大地主でもあった。財政は、徳川家の家政、宮廷官房の延長線上にあったのである。
つまり、近年まで貨幣経済ではなく、物経済だったのである。現代のような貨幣中心の社会になったのは、紙幣を中心とした近代貨幣制度確立された以後である。この点を理解しないと貨幣制度や財政問題の本質は理解されない。
物経済では、貨幣と言っても物質的な裏付けが確保されていた。しかし、表象貨幣の時代、特に、不兌換紙幣の時代になると貨幣から物としての価値は失われ、物としての価値が信用に置き換わってのである。
その事によって貨幣は、物としての頸木(くびき)、制約から解き放たれることになる。
物の経済の時代と貨幣経済とでは、財政赤字の意味を大きく違ってくる。物の時代の財政赤字は、物の不足により、それを補う形で貨幣が使用された。又、財政赤字と言っても物としての裏付けは常に担保されていたのである。
それに対し、貨幣経済下における財政赤字は、貨幣的事象なのである。だから、貨幣の働きによる貨幣の必要量が問題となるのである。
経済は、貨幣だけで成り立っているわけではない。経済は、人的な要素、物的な要素、貨幣的要素の関数である。経済を成り立たせているのは、人、物、金の集合である。
経済には、物的経済、人的経済、貨幣的経済がある。物的経済の運動量は、生産量であり、人的経済の運動量は、労働量であり、貨幣経済の運動量は貨幣量である。そして、いかにこれらを均衡させるかが重要なのである。
物的経済、人的経済、貨幣的経済を結び付けているのは、分配であり、その分配の基準は労働によって構築される。故に、経済は、労働と分配なのである。
この労働と分配を仲介するのが貨幣である。経済の実体は、物と人にあり、貨幣はあくまでも蔭である。
大量生産の落とし穴は、生産と労働とが不均衡になることにある。即ち、生産量と労働量の均衡が保てなくなり、労働と分配を仲介する所得の量が減少してしまうのである。それを解消するためには、労働の質いかに取引の中に織り込むかが鍵になるのである。
損益は会計上の問題と限ったものではない。物的な損益、人的な損益、資金的損益もある。
例えば、減価償却が好例である。減価償却とは、一般に会計処理上の問題として捉えがちである。しかし、減価という事象は会計上の問題だけではない。
一口に、減価には、どの様な事象があるのか。減価償却の意味を知るためには、減価という事象の実態を知る必要がある。減価というのは、本来、物理的な要素が強いものなのである。
会計的な意味での減価以外に、物的な減価、人的な減価、資金的な減価が考えられる。
物的な減価には、劣化、老朽化、寿命、陳腐化、故障等がある。また、人的な減価には、技能や知識の劣化、陳腐化、人件費の上昇、専門家の育成などがある。資金的な意味での減価には、借入金の返済、資産価値の劣化、更新資金・買い換え資金の貯蓄、また、保守修繕費用、検査費、保険費等と言った費用面からも捉える必要がある。
そして、経済や経営は、例えば資金計画や保守保安計画、生産計画等、会計以外の要素の働きによって決まる部分が多く含まれていることを忘れてはならない。期間損益を検討するためには、会計以外の部分の働きが利益にどの様な影響を与えるかが重要な鍵を握っているのである。
貨幣価値は、極言すると自然数である。故に、貨幣経済は、自然数の集合である。貨幣単位は、数直線である。自然数は無限に拡散する。故に、貨幣価値も無限に拡散する。貨幣価値を抑制するのは、人と物の経済である。
貨幣価値は、自然数によって表現される。自然数は無限の広がりを持つ。故に、貨幣価値は、抑制を失うと際限なく膨張するのである。
それに対し、物は有限である。物には、物質的な制約がある。人の力にも限界がある。人間が与えられた時間は、限りがあるのである。人は、必ず死ぬのである。これも仮定である。しかし、誰もがそれを自明だと信じている。それが重要であり、大前提となるのである。
数とは、対象の属性を数的なものに特定し、他の属性を削ぎ落とすことで成立する。対象から数を抽出することによって数学は成り立っている。そして、数学が成立することによって近代という時代の礎は形成された。しかし、それは同時に、対象から、数字以外の意味を喪失させる結果も招いている。
先ず一という長さがあり、それを例えば、十個繋げると十という長さになる。その一の長さを一メートルとしたときはじめて十メートルが測れるのである。
一という数があり、そこから、十という数やメートルという単位が派生しているという事である。
一つの物があり、それを十集めると十になる。その一を一個とする。その一個の物を十円とする。そうすると十個の物は百円になる。この様な関係が成立する。
ここでも一という数があり、十という数や円という単位が成立している。
一つの物がある。その一つの物を一個のアメとする。それを一つの十円玉と交換する。そうすると一個の飴は十円となる。
ここでは、一という数と一個という単位と一円という単位が掛け合わされて、一つの貨幣価値を形成しているのである。
注意しなければならないのは、対象自体に一という属性はない。一という性格は、他との関係から生じる。即ち、一という数は、何等かの他の存在との比較の上に成りたっているのである。
対象持つ意味や属性を数値に置き換えることは可能である。例えば、時間や場所、対象、仕事と言った意味を数字で表すことは可能である。逆の操作で言えば、数値に時間、場所、対象、作業と言った意味を持たせることも可能となる。この様に意味や属性を数値化する事によって意味や属性の働きだけを取り出すことも可能である。
この様に対象の属性や意味を数値化し、集合とする事ができれば、複雑な概念も集合や群を構成する事が可能となる。
この様な働きの中で重要なのは、数の位置と順位である。それが数の大小、前後などを表す。又、数は、数えることを事を可能とする。数えることが可能だと言うことは、計算を可能にすることを意味する。
又、貨幣の働きは、交換にある。交換のために、数の属性が重要となるのである。
物の価値は、使用価値であり、実質価値である。貨幣価値は、交換価値であり、名目価値である。
経済では、数とその持つ意味が重要なのである。数学とは、抽象化の過程であるが、経済はその最後に現実に結び付けられなければならない。故に、経済では、最終段階において、数を現実の対象に還元することが要求されるのである。
数と貨幣との関係は代数的な関係である。
貨幣価値は、数への変換を二重にすることによって成立する。第一段階で物や労働の量への変換であり、次ぎに、物や労働の量を貨幣価値に変換するのである。
価格には、単に、数値的な意味だけでなく、数値以外の情報も本来含まれている。つまり、価格というのは、単位あたりの値段と価格が指し示す財の量の積である。
この様に、数値化する事によって次元の違う対象間の演算も可能となる。しかし、価格だけでは、一体その価格が何を指し示しているのかは解らない。パンの価格なのか、チョコレートの価格、ケーキの価格なのかは、値段を見ただけでは解らない。又、同じケーキでもどの様なケーキで、どこのメーカーのケーキ、又、ケーキはどれくらいの量あるのかも解らない。実際の商品を見てみないと値段が妥当であるかどうかの判断は付かない。
例えば、労働と仕事を足したり引いたりすることも可能となる。しかし、それだけでは、経済としての用をなさないのである。貨幣価値は、最終的に、現実の財に交換されることによっじつげんする。
数が交換価値と結びついて貨幣を生んだ。
貨幣は、当初、物としての価値から交換価値だけを抽出し、表象化することによって成り立っていた。交換価値とは、数である。それでも、金貨や銀貨は、物として価値を併せて持っていた。
物としての貨幣と表象としての貨幣は、本質的働きが違う。
物としての貨幣は、債権ではないので、債務を生じない。故に、金貨や銀貨で貨幣を賄えたうちは、公的債務は生じないのである。金貨、銀貨が不足するとそれを補う形で、表象貨幣が生じたのである。そして、俗に言う、債務のレパレッジ効果が成立するようになる。
植民地から流入する金や銀が潤沢なうちは、金貨本位、銀貨本位の貨幣制度が成立していた。金や銀が不足することによって兌換紙幣、そして不兌換紙幣の時代に変化していったのである。
兌換紙幣は、預かり証が原形であり、金と交換する権利を表象するものであり、物の価値を裏付けとして持っていた。しかし、不兌換紙幣になるとその裏付けは国債、つまり、権利を表象するだけとなったのである。つまり、抜け殻のようなものであり、あるのは国家に対する信認だけである。
金貨、銀貨は、物としての価値も併せて持つ。故に、物としての相場の影響を受ける。金や銀の価格の変動の影響を直接、間接に受けることになる。兌換紙幣にも同様の制約を受ける。不兌換紙幣は、この様な制約から開放される反面、公的債務による制約を受けることとなる。
貨幣は、価値を抽象化することによって成り立っている。しかし、貨幣に限定して言うとそれが貨幣の欠点でもある。貨幣価値は、物や用役に還元されてはじめて意味を持つ。
会計がわかりにくいという意見がある。会計の根源に貨幣が存在しているからである。会計的価値は、貨幣的価値であり、物や人と直接的に結びついていないからである。そして、貨幣価値は数値的価値だという事である。
会計がわかりにくいというのは、会計的対象が、図形的、映像的な対象ではなく、数値的対象だと言う事に起因していると思われる。その為に、対象を直観的に認識できないことがあると思われる。
しかし、数値の背後には、生々しい物的な対象が隠されているのである。
貨幣経済は、人の一生や家族、社会と言った人に纏わる人の経済、衣食住と言った物の経済の上に、成り立っている。ところが貨幣が取引の仲立ちをしている内に、あたかも貨幣が全能であるかの如き振る舞いを始めたのである。それに人間の強欲が拍車を掛けた。
今、家を建てようとすると、大工と建築資材、建築費の三つが必要となる。考えてみると、この三つの要素の中で大工と建築資材があれば、家を建てようと思えば建てられるのである。建築費は、絶対条件ではない。
つまり、経済を実質的な部分で成り立たせているのは、人と物である。
ところが現代は、「お金」がなければ家は建てられない。それが貨幣経済なのである。
家を実際に建てる時に先ず必要とされるのは、設計図である。むろん、予算も大切である。しかし、設計図がなければ家は建たないのである。次ぎに工程表である。そして、強度計算。いずれにしても物や人にに関連した計算が必要となる。「お金」の計算だけしても家は建たないのである。ただ、今日では、家を実際に建てるのは、工務店や建設会社であって施主の最大の関心事は「お金」の問題である。だから、経済を「お金」の問題と、限定的に捉える傾向があるのである。
しかし、経済の本質は、人と物の経済にある。
物の数の数える手段は、単位、助数詞から成る。物の値段は、この単位、助数詞と単価の関数である。
助数詞とは、物や人を数える際の基準である。その意味で助数詞は、数と物とを結び付けている概念である。
我々は、物の数を数える時、一つ、二つとだけが数えたら何を数えているのか解らない。豆腐、一丁とか、船が一艘、子犬が一匹、お米が一俵、お菓子が一袋、ビールが一ケースと助数詞をつけることで、具体的な対象に結び付けることができる。それが助数詞の役割である。助数詞は、対象の一つの塊の全体を表す単語なのである。
この助数詞は、経済の在り方を暗示している。即ち、経済的数というのは、単位、或いは、助数詞と単価が組み合わされた概念なのである。
先ず物的な経済の根本というと、人間が生きていくために必要なものがあげられる。人間が生きていくために、必要な物で、一番にあげられるのが衣食住である。これが、物的経済の根底を成すことになる。
そして、人間が生きていく上で欠くことができない関係に人と人との関係がある。この人と人と関係を維持するために必要な物資が、物的経済の付随的要素となりのである。
衣食住を考える上では、先ず必要量を計算する。その上で消費量を調べるのである。次ぎに、生産量が問題になる。生産量も生産地が重要になる。生産地から消費地までの距離が問題になねのである。生産地から消費地の距離によっては、運送経路と運送手段を知る必要がでてくる。その為には、地理的な条件、地質学的な条件、地政学的な条件を予め設定しておく必要があるのである。
つまり、物的経済というのは即物的経済であり、それだけ人々の生活に密着していることになる。
そして、物的経済の根底になければならないのは、国家観や人生観であり、又、風俗主観と言った文化的な要素なのである。
気候、風俗に基づく食文化や服飾文化、建築文化が物的経済をの基盤となる。つまり、経済とは文化なのである。
経済というと、つい「お金」の話だと思われがちだが、今日の経済の基盤には物の革命があったことを忘れてはならない。産業革命に端を発し、科学技術の発達の結果、大量生産方式が博く社会に浸透したことが経済の基盤を作り上げたのである。むしろ、物の革命に「お金」の制度がついていけないのが、経済の混乱を招いていると言ってもいい。
産業革命、農業革命、生産革命、エネルギー革命、交通物流革命、情報革命、通信革命と言った物的技術の革新があったからこそ現在の経済は安定していられるのである。
近代経済学では、恐慌や不況の原因として専ら貨幣の振る舞いが問題にされ、物質的問題がないがしろにされる傾向がある。しかし、実際は、物的要因は、貨幣的要因に勝とも劣らない影響を与えている。
だからこそ物の経済の在り方こそが経済の基盤をなしているのである。
享保の飢饉の際、百両の大金を首から提げたまま餓死した商人がいたという記録が残っている。この男は、百両の大金を持っていたのに、米一粒、買えないで飢え死にしたのである。飢えた時に必要なのは、食べ物であって、金ではない。例え、金がなくても、植物に対する知識、知恵があれば、野草を食べて生き残る術もある。経済の根本は、物の経済である。(「近世の飢饉」菊川勇夫著 吉川弘文館)
根本は、自分が、或いは、社会が生きていく為に必要な物資、物は何かである。それは現実的な話であり、空想的な話ではない。
例えば、水や食べ物である。
一人の人間が生存するために必要な食料の一日の最低限度量は、どれくらいなのか。食料の実際の消費量はどれくらいなのか。一体、日本人は、どの様な種類の食べ物をどの様に消費しているのか。これは食文化の問題である。それに対して、日本の食料の生産量はどれくらいなのか。日本はどれくらいの食料を輸入し、又、輸出しているのか。日本の食糧自給率はどれくらいなのか。日本の食料備蓄量はどれくらいなのか。日本の耕地面積はどれくらいなのか。食糧増産の可能性はあるのか。日本人の食料の生産地はどこなのか。どの様な経路をとって、どの様な手段で食料を運送しているのか。これらの事を前提としてそれを貨幣に還元するのである。経済というのは、最初に「お金」ありきではない。
それでなくても、日本の食糧自給率は低いのである。国際市場の中で生き抜く知恵がなければ、国民は、忽ち、飢えることになる。それが現実であり、日本人に、禁物なのは奢りである。
人々の生活を成り立たせている生命線、ライフラインも、物の経済を考える上で重要な要素の一つである。即ち、地理的条件、地質的条件、地勢的条件である。
港湾、空港、鉄道、道路、通信、水道、鉄道、電気、ガスといった社会の基盤(インフラストラクチャー)も物的経済の基盤である。
物的経済で重要な要素の一つが距離であるが、距離も単純な長さの単位だけでなく、時間を加味した時間距離や費用を加味した貨幣的距離などもある。つまり、経済的距離とは、経済的に見て、最も最短距離は何なのかの問題なのである。
こう考えると物の経済の根本は国家観、世界観に基づくことになる。どの様な国にするのかがあって、つまり、国の設計図や青写真があってはじめて、物の経済は成立するのである。
そして、どの様な国にするのか、どの様な社会を実現するのかという物質的構想の上に国家財政や家計、企業経営が成り立つのである。「お金」の為に経済は成り立っているわけではない。
現代は、まず「お金」が問題になる。売るために製品を作るのであり、「お金」の為に財政が活用される。本当に必要な物かどうかが判然としないままに物が浪費される。
人生設計がないままに、「お金」のために働いているようなものである。それでは主体的な生き方などできはしない。
資源の無駄遣いも、環境破壊も、物の経済が忘れられているからである。だから、節約も倹約も空疎でしかないのである。
本当に必要な物なのか、どうなのか、その根本が何ら問われることなく。ただ、金のために経済があるかのように錯覚しているのが原因なのである。
物の経済こそ確立されるべきなのである。
科学的な数学と技術的な数学がある。科学としての数学が無限を追究すれば、技術としての数学は、限界に挑戦をする。
科学技術の発達と言うが、人間が驕慢になった時、自然界から強烈なしっぺ返しを受けることになるだろう。それは、人間は自然環境の中でしか生きられないからである。環境を破壊するのは、自分達の生存空間を狭めているのに過ぎない。
人は、豊かになると天を嘲笑うが、災難に逢うと天を呪う。しかし、天は天である。自然の恩恵である資源を必要としているのは人間である。自然界が人間を必要としているわけではない。自然は自然なのである。自然環境は、一度失われれば元通りには戻らないのである。
科学というのは、本来、世俗的なものである。科学万能というのは、間違った信仰である。万能な存在は神でしかない。経済も又然りである。神を否定する者は、自らを神とす。怖れるべきは、人間の強欲であり、驕慢である。



このホームページはリンク・フリーです
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures
belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout
permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2009.12.20 Keiichirou Koyano