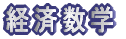全一なる存在と唯一の存在。
一には、二つの意味がある。
己(こ、個)としての一と全体としての一である。この二つの一が認識の始まりとなる。
己としての一は、自己の一である。自分の命は一つである。自分の肉体も一である。自分は、唯一全体な存在である。自分の人生も一つである。
全体としての一は、存在の一である。対象の一である。唯一の存在として一である。世界全体としての一である。
そして、全てはこの一から始まる。この一の持つ二つの意味が二を生み出す。一が二となるのである。そして、二が三となる。
ゼロは、存在であり、無限である。一は、自己であり、自己は一である。自己は。、対象に投影されて単位となり、対象は、単位を切り取られて一となる。単位は、自己に反映されて二を生む。二は、自己に還元されて三となる。神は、ゼロであり、無限である。意識は、ゼロと一と無限の間に生じる。
自己と全体、自己と対象とは一対一の関係にある。自己と全体が統一されて絶対的存在となる。それが全ての認識の前提である。
人が生まれて初めての認識は、直観に基づく絶対的認識である。それは、存在に対する認識である。
最初は、全体を一つの塊として認識する。その段階では、まだ、意識は、無分別である。全体が一つの時点には、存在は絶対で完全無欠である。全体を一つの塊として捉えていたら個々の対象を識別することはできない。
故に、最初の認識をした直後に分別が始まる。分別が始まった瞬間から全ての認識は、相対的となり、絶対的認識は終了し、意識が活動をはじめる。
故に、意識による活動は、全体を分かつことから始まる。
二は、識別の始まり。
数の始まりは、対象を分かつことである。一つの全体は、幾つかの部分に分かつことによって数に対する認識が形成される。
数学を、現代の学校教育では、代数を基礎として教える。数学の基礎は、むしろ幾何学的な概念である。ところが、代数を中心に教えるために、幾何学的な要素が抜け落ちてしまうことが多い。これが後々重大に欠陥となるのである。
近代数学の祖となるギリシアでは、数学の道具は、専ら、定規とコンパスであった。その定規も現代みたいの様に長さを計測する目的の物ではなく。直線を引く目的の物であった。コンパスの目的は、円を描くことと、線分の長さを他の直線上に移し換えること、角度を別の場所へ移動させることでしかない。(「無限を読み解く数学入門」小島寛之著 角川ソフィア文庫)
幾何学的に言うと数とは、一定の線分である。それは、一という長さの量を決める。その一と決められた線分に対して、二の線分、三の線分が成立するのである。
そして、足し算は、一の線分の延長線上によって計測される。それが計算の始まりなのである。
このようにして成立した量が数に変換されることによって数学は形成されたのである。
数の概念は、数単独に成り立つ概念ではなく。自己と対象との関係や認識上の操作から派生する構造的概念である。これは言語も同様である。故に、数も言語も操作によって成り立っている体系なのである。
主観的数の観念と対象のもつ形式的属性が結びついた時、数の概念が確立される。
全体を認識する自己は一である。故に、全体を分かつ自己は一である。しかし、自己は間接的認識対象である。故に、対象を分かつことによって、自己の存在を認識する。対象を通じて間接的に自己を認識する事によって、対象を認識する前の自己と、対象を認識した後の自己との間に意識の差が生じる。それが二となり、三となる契機となる。
自己を対象に投げ出し、投影することによって自己を客体化する。その時、対象の絶対性、完全性は破れ、相対的な対象になる。それによって対象間の一対一の関係が成立する。
数には、一つ、二つと数え上げていく数と、全体を一とし、又、部分を一とし、その比によって成り立つ数がある。数え上げていく数には、際限がなく、全体を一つとする数には限界がある。この二つの数に対する認識の仕方は、明確に区別がされているわけではなく、設定される条件によって使い分けされている。問題なのは、前提とされる設定が常に、いい加減だという事である。
貨幣価値は、閉ざされた空間の中で効果が発揮される。貨幣は、本来、後者である。
今日の経済は、有限な世界を前提として成り立っている。ところが、貨幣経済は、際限なく拡大を続けている。それが、現代社会の矛盾の一つである。
数えるという行為は、経済と不可分な関係にある。数を数えるという行為は、文化的な行為である。
数には、限りがないが量には限りがある。数量とは、限りのない数と限りのある量が組み合わさって構成される。経済的単位、経済的価値は、数と量、即ち、数量によって表される。
経済とは、生きる為の活動である。生きていく為には、生きていく為に必要な物がある。人間が生きていくために必要とする物には限りがある。
人間が生活するための住空間は有限である。しかし、地価に限りがあるわけではない。地価は、上昇しはじめると際限がなくなる。経済的価値は、この二つの要素の調和によって成り立っている。
それに対して貨幣価値には限りがない。貨幣価値は、限りなく上昇させることが可能である。物の量と貨幣価値が示す数によって経済価値は構成される。
経済とは、生きる為の活動である。生きる為の活動の根本は食べることである。人間は生き物であり、食べ物を食べなければ生きていけない。そして、人間は、一人では生きていけないのである。少なくとも、生まれたばかりの赤ん坊は、誰かが世話をしなければ食べることどころか、移動することすらできないのである。親に迷惑をかけない子供はいないのである。
人間は、生きていく為には、自分を支える人間関係を前提としなければならないのである。つまり、人間は、自分が生きる為には、食料を得る事と他の人間との関わりを前提としているのである。
先ず生きる事が前提となる。故に、生きる為の活動が全てに先立つ行為である。
昔、人々は、獲ってきた獲物や収穫物を分け合って生きてきた。いかに公平に分け合うか、それが経済の始まりである。故に、数と経済は、最初から切っても切れない関係にあるのである。
公平に獲物や収穫物を分かつためには、幾つに分かつのかという数と幾つあるのかという二つの数を数えなければならない。幾つに分かたなければならないのかは、主体的数であり、幾つあるのかは、客観的数である。数の成立には、この主体的数と客観的数の双方が必要なのである。
なぜならば、数は認識上に於いて派生した概念だという点である。又、数は、抽象的概念だと言う事である。認識上に於いて派生したという事は、相対的だと言うことである。抽象的概念だと言う事は、何等かの実体を前提とし、合意を前提としているという事である。
主体的数とは、自分の数、内なる数を意味し、客観的数とは、対象の数、外なる数をも意味する。
その対象が物なのか、主体的存在なのかによって数の働きにも違いが生じる。対象が物である場合は、物理的単位を形成し、主体的存在である場合は、経済的単位、即ち、貨幣単位を形成する。
即ち、数は、対象を認識する行為と対象を再構成する行為の二つの行為によって成り立っている。それは、帰納的な論理と演繹的な論理に引き継がれていくことになる。数には、数えると言う要素と数えられるという二つの要素があるのである。
客観的数字は、在る数字であり、主体的数字は、位置付けられる数字である。そして、在る数字は、基数となり、位置付けられる数字は、序数となる。
計算という行為が経済的行為を発展させる。捉えた獲物や収穫物を分解し、それを再構築して分配する。それが数を数えるという行為の根底を成す。
ある全体を一とし、それを分割した部分をも一とする。全体の一と部分の一とを比較する事によって単位を設定する。それが一の始まりである。そして、数は一より始まる。
故に、分かつという行為が、経済と数の概念の前提となる。そして、分かつと言う事は、対象の認識の始まりをも意味する。なぜならば、認識は識別を意味するからである。
数の始まりは対象を分かつことである。なぜならば、数は対象を認識することを端緒とするからである。認識は、対象を識別することである。識別すると言う事は、対象を分割することである。故に、数は、対象を分かつことによって生じるのである。
分かつと言う事は、比である。数えると言う事は量である。比は主体的数字である。量は、客観的数字である。
対象は連続的な物であり、数は分離的な認識である。
物としての対象は、質量と形相からなる。物は、質と量からなり、質とは、対象の持つ固有の性格を言う。数とは、対象の形相で量的な部分を抽象化した概念である。
物には、素材と外見がある。素材とは質料であり、外見とは、形相である。
人間は、魂と肉体からなる。魂とは質であり、肉体とは形である。人間とって精神と姿勢が大切なのである。精神とは、質であり、姿勢とは形である。
数は形から導き出される。
数を数えるとき、ただ、一、二、三とばかり数えるわけではない。一匹、二匹とか、一冊、二冊、或いは、一個、二個と最初は、数字だけでなく、背後にある何物かを想定して数を数える。質と量は未分化である。数は数としてのみでは成立していないのである。数の概念は、物から離れることによって抽象化される。
対象は、本来連続的な世界である。分別は、認識によって生じる。つまり、全体を部分に分割することによって対象は識別され、認識される。認識によって対象は相対化される。対象を相対化するのは、自己であり、対象が最初から相対的なのではない。自己が対象を認識するために相対化するのである。それが識別である。そして、対象が識別されることによって分別が生じる。
数える対象というのは、本来、連続した物である。それを数えるために分割するのである。そこから量の概念が形成される。量は、連続と分割の中間に存在するが年である。
故に、量には連続量と分離量がある。
飲み物を考えれば解る。飲み物は、液体としての全体がある。それをコップに飲む量に分けて一人一人の配る。飲み物は、連続体なのである。それが器に分けられる行為によって一つの単位を形成し、分離量に変換される。
対象を認識し、測り、そして分かつ。それを集め、数え、配る。その過程で一対一の関係が生じるのである。それが数の始まりである。
つまり、最初、対象は連続的な物で在る。それを分離する事によって対象の性格付けがされるのである。それが意味である。数も対象から抽出された性格の一つである。
そして、分割された部分を幾つかの塊に集めて、数の体系を再構築するのである。
幾つかの数を集めて一つの塊を作り、それを一として、一つの単位とする。同じ量だけの数を集めて塊を作り、それを二とする。集めた数と同じだけの塊ができたら、それを集めて新たな単位を作る。この様にして単位に階層を作ることを位取りという。そして、一つの階層を桁という。集めた数が、二つならば二進法と言い、三つならば三進法という。現代一般に使われているのは、十進法、即ち、十を一つの塊としている。n桁の数は、塊の最小単位の数のn乗を意味する。例えば、百の位は、十の二乗を掛けることを意味する。
又、この様な数の体系は、ゼロを意味する集合と単位を意味する集合を設定する事によって成り立っている。
数の体系が再構築された上で、集められた塊に普遍的な性質だけが抽象化され、名前が付けられて数が数えられるようになるのである。それが数詞である。数詞には、基数詞と序数詞とがある。数と数詞は一対一に対応している。
全体を一つの塊としてその塊が開かれていて際限がない対象を無限とする。閉じていて限界が設定されている対象を有限な対象とする。
対象を無限とするか、有限とするかによって対象に対する捉え方、認識は、まったく違ったものになる。
例えば、経済を無限な対象と見るか、有限な対象としてみるかによって経済施策は百八十度違ったものになる。
数字には、人的な数字と物的数字、指標的数字がある。指標的数字とは、尺度的数字であり、貨幣的数字である。
人的な数字とは、主体的数字である。即ち、認識主体が一とする数字である。それに対し、物的数字とは、客観的な数字であり、一となる数字である。そして、尺度的な数字、指標的数字とは、仲介的数字であり、一を指し示す数字である。
豊臣秀吉は、立木を数えるときに、立木一本一本に紐を結び、その紐を集めて立木の数を数えたという。主体的数字とは、豊臣秀吉が数えようとする数字であり、客観的数字とは、立木の数であり、指標的数字とは紐の数である。(「数学入門」(上・下)遠山 啓著 岩波新書)
そこで使われた紐が数字の素(もと)であり、やがては貨幣へと発展するのである。数の素(もと)は、素(そ)である。即ち、名はない。石や紐と言った単一的な物である。貨幣では貝の様な物である。つまり、数という性格を象徴した物であれば何でもいい。数という性格を象徴するには、できれば、何の装飾もない素の物がいい。
数は最初は一でしかない。
通常、何等かの対象に一対一に結び付けられて数の素(もと)は、名付けられる。数の素を名付けた表現が数詞である。
一般には、自分の身体の一部に結び付け一対一の関係によって数字は識別される。それも全体を部分に分かつことによって成り立っている。
数の素が十個集まった集合を一つの塊とするのが十進法である。現代、我々は、十進法を基本として考えるが、最初から十進法によって統一されていたわけではない。現に、時間は、現在でも十二進法と六十進法の混合したものである。
イギリスの貨幣単位は長いこと十二進法を基本としていた。
コンピューターは、二進法を基礎とした体系の上に構築されている。情報産業の発達は、二進法的世界を拡大する結果を招いている。
数には、数えるという側面と測るという二つの側面がある。数えると言う事と、測ると言う事の違いは、分離量と連続量の違いであり、数の本となる対象が連続した対象か、不連続な対象化の違いでもある。
数値とは、量と比を表している。数えると言う事は、対象を一個の全体として先ず認識する事にある。次ぎ、それを自己と対象との間で一対一として認識する事である。そして、其の後、最初に認識した対象と他とを比較することである。故に、数の最初の認識は、他との比較に基づく。
数が連続量から分離量への変換の過程で生じるのであるから、数の本質は比である。
先ず、一という事、一の成り立ち、一の持つ意味が重要である。一は単位になる。何を一とするのかが重要となる。そして、それを何と比較するかである。比較する対象は、相似的対象である。
我々は、単位という1メートルとか、1キログラムと言った最初から決められた、所与の値と思いがちである。しかし、それは普遍単位を言うのであって、単位の原初的形態は、その時点その時点に任意に定める個別単位である。その時その時に一と決めたものが個別単位なのである。
任意に決められた一定の線分があって一メートルと言う単位が決められる。一メートルという単位が先に、所与としてあるわけではない。
単価というのは、単位価格を言う。単価は、個別単位である。また、単価は、取引条件によって決まる未知数でもある。それが経済現象と自然現象の決定的な違いである。
単位というのは、一となる値である。
一から二が生じ。二から、三が生じる。一と、二と、三が生じると、一と二と三に順序が生じる。それが数である。数は、何等かの指標に結び付けられて認識されるようになる。
一対一の関係が成立しただけでは、数の概念が確立したわけではない。数は、量という概念に結びつくことによって始めて数の概念は成立する。全体を分割しただけでは、量の概念は確立されないのである。量の概念は比によって確立される。そして、分割された部分が、数詞、例えば一、二、三という言葉に、一対一に対応することが必要なのである。
時は、連続量である。貨幣は、分離量である。
連続量である時を一定の長さで区切り、分離量に変換する。時を分離量に変換することによって時間の単位は設定され、時間が定まる。時間の性格は、時の長さをいかに区切るのかの仕方によって決まる。
時間の単位を決めるのは、天体の運行である。太陽を基準とするか、月を基準とするか、何を基準とするかによって時間の在り方は様々に変化した。
現代人は、数学が数学として確立された後に生まれた。故に、数学という学問は、独自の閉ざされた空間の中で成立しているかの如く錯覚している。しかし、数学は程、全ての分野に通じる学問はない。
数は本来数だけで単独に成立するのではなく。複数の要素が関係し合うことによって形成される概念なのである。
数に属性を加えられた物が量である。属性には、長さ(L)、質(M)量、時間(T)などがある。(「使える数理リテラシー」杉本大一郎著 勁草書房
)
数の属性は次元を形成する。次元とは数の属性である。故に、量には次元がある。
長さとは、距離を表す基準である。距離は位置の概念の一つである。故に、数は位置の概念である。
数は、量的な位置に結び付けられ、順位が付けられる。
秩序は、順序、位置付けに始まる。順序、位置付けは、決め事である。秩序は決め事である。数は、順序づけられ、位置付けられることによって秩序が与えられる。
量の種類には、長さ、時間、質量などがある。
貨幣単位の基準は、距離や重さのような何等かの物理的な実体の裏付けがあるわけではない。その時点、時点の取引の結果として定まる相対的な基準である。
数は部分である。故に、一対一の対応、分割、順序の変更に対して不変、即ち、総量は同じである。(「数学入門」(上・下)遠山 啓著 岩波新書)
貨幣単位は、物理的単位とは違う。貨幣単位は、主体的単位である。メートルやグラム、リットルと言った単位と円やドルという単位は、異質な単位である。それは、単位の設定手段を見ても解る。物理的単位というのは、予め合意に基づき設定された定義による。それに対して貨幣単位は、取引に基づくのである。貨幣は、量的な単位ではなく、操作的な単位である。
貨幣は、分離量として表現されるが、量的に定義化されるわけではない。量的定義とは、何等かの対象に結び付けられた定義である。貨幣は、それ自体で何等かの質量を持っているわけではない。ただ量のみを示しているのである。即ち、貨幣は、固有の性質を持っていないのである。貨幣は、他の対象と掛け合わせることによってはじめて成立する単位なのである。つまり、貨幣単位は、他の対象と掛け合わせることによって価値が成立する。
貨幣は、対象の交換価値を数えることによって本来連続量である交換価値を分離量に置き換えるのである。そして、分離量に置き換えることによって計算を可能とする。
即ち、貨幣価値とは、財の単位量と財の単価とを掛け合わせることによって出された解であり、その操作によって個々の特殊な価値が汎用的価値に置き換えられるのである。そのことによって異質の財の間の演算かが可能となる。財が汎用的価値に置き換わる事によって成り立っているのが市場である。
物理的数学と、経済的数学の違いは、物理的数学では物理的に異質な物、例えば、牛と自動車とか、労働と電気とは演算できないが、経済的数学の上では可能なのである。
それを可能とするのが、貨幣単位と単位量とを掛け合わせる操作であり、貨幣単位は、財の単位量と掛け合わせるという操作を前提としたの単位なのである。
経済では、数とその持つ意味が重要なのである。数学とは、抽象化の過程であるが、経済はその最後に現実に結び付けられなければならない。故に、経済では、最終段階において、数を現実の対象に還元することが要求されるのである。
貨幣単位は、自然数の順序集合である。一つの貨幣単位は、一本の数直線として表現される。貨幣単位の基礎となる数直線は無限である。貨幣の単位は、複数の貨幣単位均衡によって保たれている。
単位貨幣間の交換は、通貨圏を跨いだ取引において財を通じて行われる場合と、支払準備として直接単位貨幣間で行われる場合がある。
貨幣価値は、自然数によって表現される。自然数は無限の広がりを持つ。故に、貨幣価値は、抑制を失うと際限なく膨張するのである。
それに対し、物は有限である。物には、物質的な制約がある。人の力にも限界がある。人間が与えられた時間は、限りがあるのである。人は、必ず死ぬのである。これも仮定である。しかし、誰もがそれを自明だと信じている。それが重要であり、大前提となるのである。
対象持つ意味や属性を数値に置き換えることは可能である。例えば、時間や場所、対象、仕事と言った意味を数字で表すことは可能である。逆の操作で言えば、数値に時間、場所、対象、作業と言った意味を持たせることも可能となる。この様に意味や属性を数値化する事によって意味や属性の働きだけを取り出すことも可能である。
この様に対象の属性や意味を数値化し、集合とする事ができれば、複雑な概念も集合や群を構成する事が可能となる。
この様な働きの中で重要なのは、数の位置と順位である。それが数の大小、前後などを表す。又、数は、数えることを事を可能とする。数えることが可能だと言うことは、計算を可能にすることを意味する。
数とは、対象の属性を数的なものに特定し、他の属性を削ぎ落とすことで成立する。対象から数を抽出することによって数学は成り立っている。そして、数学が成立することによって近代という時代の礎は形成された。しかし、それは同時に、対象から、数字以外の意味を喪失させる結果も招いている。
注意しなければならないのは、対象自体に一という属性はない。一という性格は、他との関係から生じる。即ち、一という数は、何等かの他の存在との比較の上に成りたっているのである。
数が単独では意味をなさないという事は、数は、数量であることを意味している。
数量は、キログラム、リットル、時間と言った連続した量と一個、一艘、一頭と言った個々独立した物として数えられる数(かず)からなる。一つ一つ数を記号と結び付けて数字を作る。
財と数とを一対一に対応させた上で、財の数と単位あたりの貨幣価値、即ち価格とを一対一に対応させる事によって取引は成立する。
先ず一という長さがあり、それを例えば、十個繋げると十という長さになる。その一の長さを一メートルとしたときはじめて十メートルが測れるのである。
一という数があり、そこから、十という数やメートルという単位が派生しているという事である。
一つの物があり、その物を仮にテレビとしよう。その一を一台とする。台というのは数詞であり、テレビの数量を表す単位である。そのテレビを十集めると十台のテレビの集まりになる。その一台のテレビの単価を十万円とする。そうすると十台のテレビの集まりの価格は百万円になる。そして、そのテレビを百万円と交換することでテレビ十台の貨幣価値は実現する。この様な交換行為を取引という。取引は、貨幣価値を実現するための操作、演算と言っていい。故に、取引は、貨幣価値と数量の関数である。
このようにして一という数があり、十という数や円という単位が成立している。
ここでは、一という数と一台という単位と十万円という複数の単位が集合して一つの貨幣価値の単位を構成しているのである。この単位集合に十台という数量を掛け合わせることで売上という集合が成立する。
この様な集合を群という。
又、貨幣の働きは、交換にある。交換のために、数の属性が重要となるのである。
数と貨幣との関係は代数的な関係である。
貨幣価値は、数への変換を二重にすることによって成立する。第一段階で物や労働の量への変換であり、次ぎに、物や労働の量を貨幣価値に変換するのである。
我々は、経済現象を認識する際、物理的量であろうと、貨幣的量であろうと、時間的量であろうと数に依る場合が多い。しかし、経済の総てが数値に表せるわけではない。むしろ経済という目に見えない事象を目に見えるようにする過程で数が使われているのである。経済には、数字で現れない部分があることを忘れてはならない。
それは、経済は、人間の営みであり、文化だからである。
参考
「数学入門」(上・下)遠山 啓著 岩波新書
「零の発見」吉田洋一著 岩波新書
「物語 数学の歴史」加藤文元著 中公新書
「古代ギリシアの数理哲学への旅」河田直樹著 現代数学社
「はじめて読む数学の歴史」上垣 渉著 ベレ出版
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2009.12.20 Keiichirou Koyano