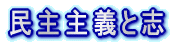最初は何もかも混沌としている。意識は深い闇の中に、眠っている。意識が目覚める時、分別が生まれる。分別によって絶対的存在は失われ、真実は意識に覆われて姿を消す。分別は、意識の覆いを取り外し、真実に近づいていこうとする。真実に近づけば近づくほど事態は混沌としてくる。意識は、又、深い眠りにつく。
知の本性は、真(まこと)である。知の本体は実である。
実とは、事実、現実、真実である。
実の対極にあるのは虚である。真がなければ実は、虚となる。
実業も、真がなければ、虚業となる。
科学技術が進歩し、多く難病が克服された。人間の肉体を動かす仕組みも明らかにされてきた。遺伝子工学の発達は、新たな生物の可能性まで切り開いたかに見える。
しかし、肝心の生命の謎が解明されたわけではない。人間は、なぜ、生まれ、死んでいくのか。死んだらどうなるのか。まったく解ってはいないのである。
対象それ自体に、意味があるわけではない。対象に貴賤があるわけではない。対象に軽重があるわけではない。対象に善悪があるわけではない。対象に上下の隔たりがあるわけではない。対象に、新旧の別があるわけではない。対象に、清濁があるわけではない。対象に美醜があるわけではない。貴賤、軽重、善悪、上下、新旧、清濁、真偽の別を設けるのは己(おのれ)である。
意識は、分別によって生じる。分別がなければ、対象を識別できない。故に、分別の基準を設けることによって意識は生じるのである。その時から対象は、相対的な物になり、不完全な存在となり、真は、隠れるのである。最初から不完全な物はないのである。不完全というのは、認識の過程で意識が生み出す観念である。
知は、成立した瞬間から不完全な物になるのである。
分別以前の知を絶対知という。
意識が目覚める前の知を絶対知という。
絶対知とは、潜在的な知である。意識の奥底にある知である。
絶対知とは、生(うぶ)な知である。
美味しい物は、味わってみないと解らない。言葉だけで説明されても理解できない。しかし、一度味わえば、すぐに解る。そして、自分の好みと他者の好みの違いや差も現れる。
百万言費やしても愛の真実を表すことはできないが、人を愛すれば、忽(たちま)ち、愛の真実を知る事ができる。
意識にとって真(まこと)は、不可知。
真は、意識によっては、直接、知る事ができない。
真(まこと)は、意識にとって実をもってを推し量る以外に知る事はできない。
意識にとって真は、間接的にしか知り得ないのである。
直接知り得ない真(まこと)こそ知の本体である。
故に、知は、真を懼れることによって成る。
真は、本来、知る事ができない。知は、知る事のできない真を本として成り立っている。知る事のできない真を本にしているところに知の難しさがある。
解ったと思った瞬間に解らなくなる。解らないと思った瞬間に知の本質が見えてくる。
真を懼れるからこそ知の本質を理解することができるのである。
真を懼れなくなった時、人は、盲目となる。
真を懼れるとは、自分を存在させる何ものかを懼れることである。
真実を懼れなくなった時、人間は、真実によって破滅する。
知に驕る者は、真(まこと)によって報いを受ける。
人の知識は、相対知である。
絶対知は、無分別知である。
絶対知は、直観においてしかできない。
絶対知は、真を知る事。存在に対する認識。
故に、絶対知は体得する知である。
真を知るとは悟りの境地である。
人は、生病老死の真実を知らない。生病老死という現象を知っているだけである。
生命の神秘は、未(いま)だに解き明かされてはいない。
人はどこから来て、どこへ行くのか、未だに、謎である。
生命の尊さは、身を以て学ぶしかない。
善は義となり、美は礼とな、真は知となる。
真善美と表裏を為すのは、偽悪醜である。
人は、自分に負けると偽悪醜を求めるようになる。
戦争に負けて日本の指導者は、真善美を棄てた。そして、価値を逆転し、偽悪醜を信奉するようになったのである。それこそが精神の植民地化を意味している。
自分に負けると人は現実は偽悪醜だと言うようになる。
現実が偽悪醜なのではない。
自分の心が真を失い。偽悪醜を求めるようになっただけだ。
知は、理(ことわり)となり信の礎(いしずえ)となる。
理は、真(まこと)にって裏付けられ、信を支える。
真に裏付けられて信は義となる。義は信を保証する。
信によって政治、経済は成り立つ。
信が失われれば世の中は乱れる。
真が隠れて、義が行われなくなるからである。
知は、信を明らかにし、実を詳(つまびらか)にする。
真は存在を本とし、善と美は、自己を本とする。
真(まこと)を真として見極めるのは自己である。
真実を明らかにするのは、自己である。
独善は、人の目を曇らせる。傲慢は、人の目を鈍らせる。独善や傲慢は真を滅する。
生まれた直後の人は、真善美を知らない。
義は、意識によって生まれる。
意識は、相対的知である。
意識は、偏見と先入観によって育まれる。
故に、意識によって成立した義は不完全である。
義を成就するためには、偏見と先入観を棄てなければならない。
無垢な目をもって知を完成させることによって義は成就する。
真(まこと)を見極め偽を見抜く目は、純真無垢の目である。
故に、知は、純を好む。
善いことも悪いことも現実を直視する純粋な姿勢。美しいものも醜いものもあるがままに受け容れる素直で純真な心。曇りない目には、純であることが望まれる。
子供は、美味しい物は美味しいという。大人は、値段を気にするようになる。風評や噂、世間の目によって目が曇りがちになる。
子供でも、少し知恵が付くと驕る。賢(さか)しらになる。そして、狡(ずる)くなる。
子供も、少し知恵が付いてくると何でも知ったかぶりする。そんなの知っているよ。解ってますと言うようになる。それは知るを知ると言い、言葉を理解していることを解っていると言っているに過ぎない。
差別用語、差別用語と賢しらに言い立てる者がいる。言葉を狩ったところで差別がなくなるわけではない。差別するのは、言葉にあるのではない。差別する側の心にある。
幼子は、純な目をもって物事の本質を洞察する。分別が生じると純粋な目を失う。それが我である。分別は、人が自律的に生きていく為には不可欠な事である。分別がなければ、自分の分別によって身の処し方を決める事ができない。
幼子が純な目を保てるのは、一人では生きていけないからである。一人では生きていけないから自分の全てを他者に委ねざるをえない。底には我が生じる余地がない。
しかし、世の中で自分の力によって自律して生きていくためには、分別がなければならない。
分別を働かせながら、純な目を取り戻さなければ真の知を得る事はできないのである。
純な目を取り戻すためには、自信がなければならない。
自信とは何か。己(おのれ)をあるがままに受け容れる事である。
自信とは、あるが儘の自分を信じる事である。
人間は、知恵が付くと、全知全能であるかのように錯覚する。
しかし、真は不可知である。人は、現象しか知る事ができない。
そして、現象は無常であり、不確かなのである。
現象は知ったと思った瞬間から解らなくなる。人の世は有為転変、移ろいやすい。万物は、又、流転する。この世に確かなものなど何もない。
一寸先は闇である。自分だって次の瞬間どうなるか解らない。
何でもない、些細な事でも、理解しているのかと言われれば、心許ない。
知っているのかと問われると自信がない。
何でもない、些細な事に潜んでいる真すら多くの人は気が付かない。知らない。
悩み苦しんだ果てに、
「嗚呼生きている。」と嘆息し、
「俺は何も解っていなかった。」と気が付いた時、真実の知が目覚める。
生きている事こそ真である。生かされている真である。
生きているという真は、生かされているという真は、己がなければ到達し得ない境地なのである。
真実を受け容れるためには、確固たる自信が確立されていなければならない。
確固たる自信が確立されていなければ、人は。真を嫌って知に驕る。
人が、知に驕ると知は、偽になる。
知に驕ると真を失うからである。
真は、善の本である。
真がなければ真は偽となり、偽は、悪と醜の本となる。
なぜ、人は知に驕るのか。
それは、知る事のできない真を受け容れられなくなるからである。
不可知な真に耐えられなくなるからである。
不可知な真をあるがままに受け容れるためには、自信がなければならない。
真実を恐れる気持ち。真理に対する謙譲、礼がなければ知の純粋さは保てない。
例えば自分である。
自分を知っていると思うか。これは難問である。自分の顔というのは、直接見ることの出来にない唯一の顔である。
それでも改めて問い直してでも見ない限り、大多数の人間は、自分のことは、一番、自分がよく知っていると思い込んでいる。しかし、自分の心の闇は見えないものである。そして、いつの間にか自分を抑えられなくなる。
先ず、自分を知る事である。
自分を知る事で独善を妨げる事ができる。
自分を知るためには、他者に映った自分を見ることである。
他者は自分の鏡。他人の欠点は、自分の欠点を写し出したものである。
人の短所を言い立てるのは、自分の短所を言い立てているのである。人の醜さは、自分の醜さである。他人に腹をたてているのではない。他人に映った自分に腹が立つのである。
他人の、欠点、短所、醜さを見て、自分の欠点、短所、醜さを知るのである。そうすれば他人に感謝する気持ちが起こる。他人を許す心が生じる。他人を受け容れる準備ができる。寛容になれる。
他人を見て、自分の欠点、短所、醜さを見て自分を知るためには、確固たる自分がなければならない。全ては自分を知るための修業である。そして、自分に克つための修業である。
他人の短所、欠点、醜さばかりを見て自分を知ろうとしないのは、自分がないからである。自分のない者は、自分を抑えることができずに、驕慢になる。
神を怖れぬ者は、自らを神とする。
真のない知識は人間を傲慢にする。賢(さか)しらにする。
知は、両刃の剣である。
確かに、科学技術や情報技術は発達によって人類は、多くのことを可能とした。また、色々なことが解明されてきた。
しかし、その結果、生み出されたのは、人類を何万遍も滅亡されることが可能な核兵器や化学兵器、生物兵器である。
又、情報技術は、金融危機を防ぐどころか原因にすらなっている。
これでは、科学技術の発達は、人間の愚かさの証左でしかない。
知を正しく人間は生かし切れていないのである。
科学者は、全知全能にはなれないのである。
人の世を滅ぼすのは、真理ではない。科学でもない。人間の奢りである。
人が滅びるとしたら、自らの驕慢によって自滅するか、神の意志によって滅ぼされるかである。
いずれにしても、真理を懼れる心がなくなった時、人類の危機は訪れるのである。
知るとは何か。それは、己(おのれ)の限界を知り、人間の限界を知り、真理の持ち力を知る事である。さもなくば、叡知はその姿を現すことができない。
知るとは、事実を知る事、現象を知る事、真実を知る事である。事実とは、事象である。事象とは、五感(見る、聞く、触る、味わう、嗅ぐ。)によって認識できる対象である。現実とは、表面に現れた現象である。しかし、事実、現実を知ったところで真実を知ったことには成らない。事実の背後にある。真を知らなければ、理解したことには成らない。
理解するとは何か。ただ上っ面の出来事を理解したとしてもそれは皮相な理解である。真実を理解したわけではない。
人間の姿形を認識できても、人の内にある魂、意志や感情、心や性格、気持ち、精神を理解できなければ、人間を知ったことにはならない。
知るとは、本来、主体的な行為である。
客観的な行為を指すのではない。
科学者は、客観的な知を是とするが、客観的な知とは、自分を表に出さないだけのことである。
よく株で失敗しないためには、美人コンテストで優勝者を予測するようにしろと言われる。つまり、美人を自分の好みで選ぶのではなく。審査員が誰を選ぶかを予測して選べて言うのである。しかし、それも主観には違いない。その様な姿勢を敷延すれば、自分がなくなるだけである。自分を自分として自覚した上でこそ、他者の視点に立てるのである。
知ると言うことは、自分が知ると言うことなのである。
情報通信技術の発達により巨大な量の情報を処理が可能となった。巨大な量の情報を処理できるようになったからと言って真実に近づいているとはかぎらない。情報の量が増えれば増えるほど、情報を扱う人間の心根が大切になる。性根が悪ければ情報量が増えれば増えるほど真から遠ざかることもある。
リーマンの破綻を契機に起こった世界的な金融危機は、知に対する過信が原因である。
倫理観や道徳観は、統計によって導き出されるものではない。統計によって万事が解決されると思いこんでいる者には、知恵がないのである。
心を正しく保つことによって良知に至る。心を正しく保てなければ、真を見失い。良知に至らない。良知は、良識の本である。
戦争が起こる確率を予測したところで何になるのか。戦争を防ぐことができなければ意味はない。
戦争が起こる確率を知り、戦争を予測するのは金儲けのためでしかない。その時点でその者は、人間としての道徳心をなくしているのである。
我々は、職業人である前に、人間なのである。
悪辣な事に知を活用するのは、人として許される行為ではない。
何のための。誰のための知なのか。
世の為、人の為に役立たない知は、かえって害悪にすらなる。
肝心なのは真を見抜く洞察力である。真を懼れる畏敬心である。
真のない知は、かえって人間を苦しめる結果を招く。
それが核兵器であり、偽りの金融技術である。
情報通信技術、そして、統計資料は、人類に福音をもたらすはずである。
ただ、それは良知、知恵を持って情報を活用した場合である。
私利私欲をもって知を悪用すれば、真と実によって人類は、報いを受ける。
純な目とは、偏らない目、洞察する目、透徹した目である。故に、大切なのは中庸である。己が神の目を持つことではない。神の目を持ったと錯覚した時から知は真から遠ざかる。純な目とは謙譲の目である。
苦情を言うと、多くの人は、解った、解ったと逃げる。実際は解ったと言いながら、何も解っていないのである。言葉を理解すると言う事と、真実を理解するというのは、違う。
人の命令を受けたとき、すぐに解ったと言う人が多い。そう言う人にかぎって、いざ命令を実行しようとすると肝心な事を聞きそびれていることが多い。
その場合、解ったという意味は、言葉の意味がわかったという事で、自分が何をすべきなのかを理解したというのではない。
何をすべきか解ったと言うが、なぜ、それを行わない。行えない。それは真の意味を理解していない証左である。
行わなければならない事は、行動が伴わなければ知ったことにはならない。行動しなければ意味がない事は、知るという事と行う言う事が一体なのである。
義を見てせざるは勇なきなり。それは、義を見ても、義を知っているわけではない。
為せば成る、為さぬは、為さねば成らぬ何事も<成らぬは人の為さぬなりけり。(上杉鷹山)
人の命令ですら知って行うのは難しい。況や、天命を知り行うのは更に難しい。
現代社会には、知に奢りがある。その証左が知識人の奢りである。
今の知識人には、信じるところがない。
信にならない知は、虚しい。
知に実が伴わないからである。
科学万能という。しかし、科学者が真を懼れなくなれば、科学は、凶器となる。凶器となって人類に仇を為す。
科学は、相対知である。絶対知ではない。
絶対知とは、真に対する懼れであり、信を根源と為す。
つまり、絶対知とは、真に対する信仰である。
真をただひたすらに信じ、敬う事である。
人は、全知全能にはなれない。
人間は、限りある身だからである。
今の知識人には、それすら知らない者がいる。
真実を懼れ自らを謹んでこそ知を生かすことができる。
知に驕る者は、真によって報いを受ける。
真実を弄ぶ者は、真の知を得ることはできない。
そして、真実を弄ぶ者は、信を失う。
過去を知っているか。
過去は明らかだという。しかし、過去は確かめようがない。
確かめようのない過去は、現在、過去、未来の中で一番不確かだとも言える。
歴史とは何か。歴史とは意識である。
知は実をもって成る。知は、真(まこと)に忠でなければならない。
知識を持つ者は、謙譲でなければならない。
なぜならば、知は、真を失えば偽となるからである。
偽は、偽善を生む。偽善は悪となる。悪は、醜を好む。
知は、前提によって変わる。立場によっても変わる。
何を信じるかによって知の本質は変わる。
又、何を知っているのかによって信の性質は変わる。
本当に知るというのは、真実を知る事である。真実を知ってはじめて理解したと言えるのである。
必要なのは、偽を見抜く洞察力である。本物と偽物とを見分ける力である。その為には、己を信じる以外にない。
偽を見抜くためには、心眼を開くしかない。知に大切なのは偏りのない目である。眼力である。眼力を磨くためには、純な心を養わなければならない。
刮目として実を見よ。虚心にしてあるがままを受け容れよ。坦懐にして全てを見よ。真実は、ただ眼前にある。それこそが真知である。
人を救済するのは叡知である。叡知は、人間の心根より発する。人間の心根が不純になった時、叡知は発揮できなくなるのである。
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、 一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2010.6.20 Keiichirou Koyano